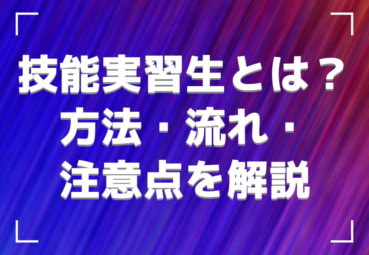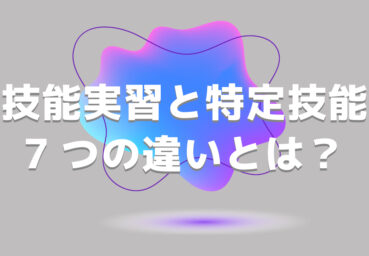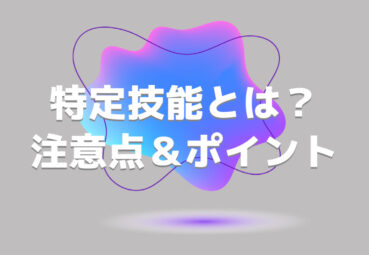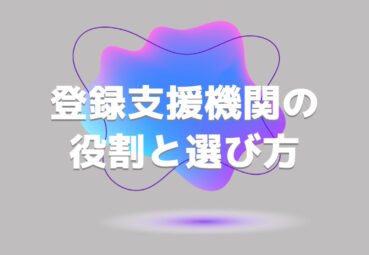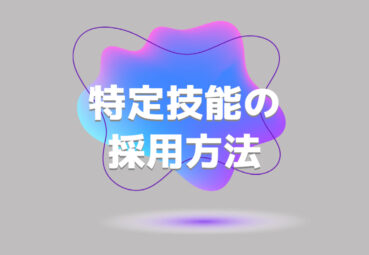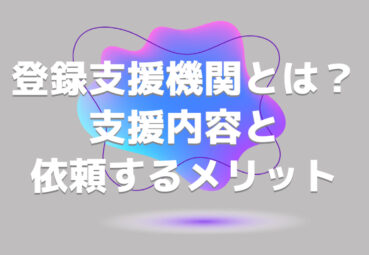特定技能関連

2024年2月27日更新
国内で多くの産業が人手不足を課題に掲げている影響で、外国人労働者の需要が増しています。外国人が取得する在留資格のなかでも「特定技能」は、即戦力としての働きが期待できるだけでなく、長期的な人材確保も実現できることから注目されています。
今回は、在留資格「特定技能」の概要を紹介したうえで、種類や対象分野、技能実習との違いなどを詳しく解説します。特定技能外国人の雇用に向けて、必要な知識を押さえておきたいという採用担当の方は、ぜひ最後までご覧ください
目次
在留資格「特定技能」とは?

「特定技能」とは、人材不足が特に厳しい分野で、即戦力としての活躍が見込まれる外国人材を確保することが目的の在留資格です。この在留資格に関して定めた制度を「特定技能制度」といい、2019年4月より導入されています。
日本には、就労できる在留資格が19種類ありますが、その多くは活動できる職種が限定的です。例えば、在留資格「教育」の活動に該当する職種は中学校・高校などの語学教師、在留資格「医療」の活動に該当する職種は医師や歯科医師、看護師などとなります。
それに対して特定技能は、国内での人材確保が難しい状況にある12の特定産業分野で、働き手を確保できる在留資格です。ほかの在留資格に比べると、対象となる業務の幅が広いといえるでしょう。
ただし、即戦力として稼働してもらうことが前提であるため、それぞれの分野に対して一定レベル以上の知識・技能が求められます。
特定技能は1号と2号の2種類がある
特定技能は次の2種類に分かれています。以下の項目では、それぞれの特徴や違いなどを見ていきましょう。
特定技能1号
特定技能1号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
|
対象者 |
特定の産業分野における相当程度の知識、もしくは経験を持つ外国人 |
|
在留期間 |
通算5年が上限(1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新) |
|
家族帯同 |
不可 |
|
技能水準 |
試験等で確認 |
|
日本語能力の水準 |
試験等で確認 |
出入国在留管理庁の報道発表資料によると、2023年6月末時点で特定技能1号を取得している外国人の数は17万3,089人です。特定技能2号を含めた取得人数を国籍別に見ると、ベトナムが9万7,490人と過半数を占め、インドネシアが2万5,337人、フィリピンが1万7,660人と続いています。
参考:出入国在留管理庁|令和5年6月末現在における在留外国人数について
特定技能2号
特定技能1号の修了者が希望し、対象者として認められた場合は2号へのステップアップが可能です。特定技能2号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
|
対象者 |
特定の産業分野における熟練した技能を持つ外国人 |
|
在留期間 |
3年、1年、6ヵ月ごとの更新 |
|
家族帯同 |
要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が可能 |
|
技能水準 |
試験等で確認 |
|
日本語能力の水準 |
確認不要 |
特定技能2号に初めて外国人が認定されたのは、2022年4月です。そのため、出入国在留管理庁の同資料によると、2023年6月末時点でも2号取得者数は12人しかいません。今後の受け入れ数の拡大が期待される在留資格といえます。
特定技能1号と2号の違いについて、詳しくは以下の記事で紹介しています。
特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説
特定技能外国人の雇用が可能な分野

ここでは、特定技能外国人の受け入れが可能な特定産業分野を、1号と2号に分けてそれぞれ紹介します。
なお、特定産業分野とは、国内での人材が足りておらず、一定の能力を持った外国人材を雇用して労働力を確保すべき産業分野です。
特定技能1号の分野
特定技能1号で受け入れ対象となっているのは、以下12の特定産業分野です。
1.介護
2.外食業
3.宿泊
4.ビルクリーニング
5.工業製品製造業
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.農業
11.漁業
12.飲食料品製造業
上記に挙げた対象業種に企業が該当しない場合は、特定技能外国人を雇用できないので注意しましょう。
なお、政府の発表によると、2024年1月時点で以下の4分野の追加を検討しているとのことです。
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業
上記分野の追加に関しては、年度内の閣議決定を目指す見通しです。
特定技能2号の分野
従来、特定技能2号で受け入れ可能な分野として認められているのは、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」のみでした。
しかし、2023年6月9日の閣議決定により、特定産業分野のうち「介護」を除く9分野と、「造船・舶用工業」の5つの区分が追加されることになりました。
【追加される9分野】
1.外食業
2.宿泊
3.ビルクリーニング
4.工業製品製造業
5.自動車整備
6.航空
7.農業
8.漁業
9.飲食料品製造業
【造船・舶用工業分野で追加される業務区分】
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
なお、介護が特定技能2号の対象分野に追加されていないのは、すでに在留資格「介護」があったためです。在留資格「介護」の在留期間には、特定技能2号と同様に上限が設けられていないので、長期にわたる就労が可能です。
特定技能の各分野については、以下の記事で詳しく紹介しています。
2023年最新|特定技能の12分野・業種の職種一覧と現状を解説!
特定技能と技能実習の違いは?
特定技能と混同されることがある在留資格に「技能実習(外国人技能実習制度)」があります。しかし、特定技能とはそもそも制度の目的に違いがあるので注意しましょう。
技能実習の目的は、開発途上国等の外国人に日本の技能移転を行い、国際貢献を図ることにあります。一方、特定技能は前述のとおり、特定産業分野における人材確保を目的としています。
両者のその他の違いについては、以下のとおりです。
| 技能実習 | 特定技能 | ||
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | ||
|
在留期間 |
最長5年 |
最長5年 |
上限なく更新可能 |
|
日本語能力水準 |
なし |
日本語能力試験 |
なし |
|
家族帯同の可否 |
不可 |
不可 |
可能 |
|
賃金 |
日本人と同等以上 |
||
なお、技能実習は政府の有識者会議によって、制度廃止に関する最終報告書が2023年11月に取りまとめられました。2024年2月9日には、新たに「育成就労制度」を創設する方針が決定しています。
法務省の「最終報告書たたき台(概要)」によると、育成就労制度では3年の就労を通じて、特定技能1号の水準に外国人材を育成するとしています。
技能実習の概要や特定技能との違い、育成就労制度の概要・基本的な考え方などについては以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご参照ください。
外国人技能実習制度とは?認められる在留資格・職種などの基本をまとめて解説
技能実習と特定技能の7つの違いとは?どちらの制度にすべきか迷ったときの考え方も
【最新動向】育成就労制度とは?基本的な考え方や重要なポイントを解説
特定技能制度で外国人を雇用するメリット
 次に、企業が特定技能制度を利用して外国人を雇用するメリットを見ていきましょう。
次に、企業が特定技能制度を利用して外国人を雇用するメリットを見ていきましょう。
外国人労働者を受け入れるメリット・デメリットに関しては、以下の記事をご参照ください。
外国人労働者受け入れのメリット・デメリットは?問題点や受け入れ方法などもまとめて解説
中長期的に即戦力人材を確保できる
特定技能1号では最長5年の就労、2号では在留期間の制限なしでの就労が可能なため、外国人材を中長期的に確保できるメリットがあります。
また、特定技能外国人には相応の知識・技能が求められるので、事業において即戦力としての活躍が見込まれる点もポイントです。厚生労働省の資料によると、介護分野における特定技能外国人の年齢は18~29歳が約7割(2021年12月末時点)を占めています。このことから、同分野の将来的な安定性も期待できるでしょう。
参考:厚生労働省|特定技能外国人とともに育つ よりよい職場づくり
技能実習生はスムーズな移行を目指せる
特定技能は、技能実習2号を良好に修めた外国人であれば、指定の試験を免除された状態で在留資格の移行が可能となっています。ただし、同じ職種の移行に限られる点には注意が必要です。
また前述のとおり、技能実習制度は廃止され新制度の「育成就労制度」が新設される方針が決定しています。そのため、今後は育成就労制度が特定技能外国人を輩出する新たなルートになる可能性は高いでしょう。
なお、自社ですでに技能実習生を受け入れている場合は、一時的に在留資格「特定活動」に変更することで、特定技能への切り替えに向けた準備を行えます。
特定技能への移行に向けた在留資格「特定活動」については、以下の記事で紹介しています。
特定技能への移行準備期間確保は特例措置で!在留資格「特定活動(4か月・就労可)」とは?
特定技能制度で外国人を雇用するデメリット
続いて、特定技能制度により外国人材の雇用を目指す際のデメリットを紹介します。
手続きが煩雑になりやすい
特定技能外国人は、自社の事業に即した外国人材を確保できる在留資格ですが、受け入れに際して手続きが煩雑になりやすい点はデメリットといえます。特定技能外国人を受け入れるにあたり、企業側は出入国在留管理庁への申請のほか、外国人の母国機関とやり取りが必要になるケースもあります。煩雑な手続きの負担を減らすために、後述する登録支援機関へ協力を仰ぐのも手段の一つです。
対象となる外国人を確保しづらい
特定技能は、各分野において即戦力となる資質を備えた優秀な外国人を対象としています。そのため、企業が独自にそのような人材を確保するのは、難しい可能性が高いでしょう。
適性の高い優秀な人材をスムーズに確保するためにも、自社の事業に見合った人材紹介サービスなどをうまく活用することが重要です。人材紹介サービスの支援を受ければ、自社の要望をしっかりとヒアリングしてもらえ、より適性の高い人材を確保しやすくなります。
外国人が「特定技能」を取得する方法は2つ
 外国人が特定技能を取得する方法は、大きく2つのパターンに分かれています。以下では、それぞれのパターンについて詳しく解説します。
外国人が特定技能を取得する方法は、大きく2つのパターンに分かれています。以下では、それぞれのパターンについて詳しく解説します。
パターン1.特定技能評価試験を受ける
1つ目は、外国人が技能試験および日本語試験に合格して、特定技能の申請基準を満たす方法です。これらの試験は国内外で実施されており、分野によって受ける試験や会場や日程などが異なります。
2020年4月1日以降の国内試験では、在留資格「短期滞在」でも受験可能になっています。以下では、それぞれの試験の概要を紹介するので、参考にしてください。
・技能試験
技能試験は分野ごとに実施されており、外国人が対象分野における業務を遂行するために必要な知識や経験を問われます。技能試験を国内で受ける場合の受験資格は、以下のとおりです。
・17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)
・在留資格を持っている
例として介護分野を挙げると、厚生労働省が主催の「介護技能評価試験」を受ける必要があります。この技能試験は日本だけでなく海外でも実施されており、問題数は45問、試験時間は60分、実施方式はCBT(コンピューターを使った試験)です。
・日本語試験
日本語試験では、日本で就労する際に必要な日本語能力を測定します。全分野共通で「日本語能力試験 (JLPT)」のN4以上、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の合格が必要です。
なお、介護分野に関しては、上記に加え「介護日本語評価試験」への合格も求められます。介護日本語評価試験では「介護のことば」や「介護の文書」などに関する内容を含む15問が出題され、試験時間は30分となっています。
特定技能制度の試験について、以下では詳しく紹介しています。
特定技能制度の試験とは?即戦力の外国人を受け入れるための基礎知識
パターン2.在留資格を移行する
在留資格の移行によっても、特定技能の取得は可能です。具体的には、技能実習から特定技能へ切り替えるケースなどが挙げられます。前述のとおり、技能実習2号を良好に修了している外国人は関連性のある業務を行う場合に、試験を免除された状態で在留資格の移行が可能です。
2020年以降は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた外国人の入国制限などを背景に、特定技能へ在留資格を移行する外国人が増加傾向にあるとされています。
特定技能の外国人労働者を受け入れるまでのおもな流れ
特定技能外国人を受け入れるための流れは、おもに以下のようになります。
1.人材を募集する
2.「特定技能雇用契約」を締結する
(※登録支援機関のサポートを受ける場合は、登録支援機関と「支援委託契約」を結ぶ)
3.支援計画を策定する
4.在留資格認定証明書の交付申請を行う
(※外国人がすでに在留している場合は、変更申請を行う)
5.在外公館に査証申請をしてビザを受領する
6.来日する
7.就業をスタートする
なお、特定技能外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関」として、各種の届出も義務付けられています。
「特定技能所属機関(受入れ機関)」として外国人を受け入れる際の注意点
特定技能所属機関は、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ企業や個人事業主を指し、「受入れ機関」とも呼ばれています。
以下の項目では、特定技能所属機関として外国人を受け入れる際の注意点を紹介します。
外国人労働者を受け入れるための基準を満たす必要がある
受入れ機関になるための基準と、具体的な条件例は以下のとおりです。
|
基準 |
具体例 |
|
受入れ機関として適切である |
・社会保険料や税金を納付している ・債務超過に陥っていない ・1年以内に外国人の行方不明者を出していない |
|
特定技能雇用契約の内容が適切である |
・報酬額を日本人と同等以上にしている ・定期健康診断を受けさせる ・一時帰国の希望者には有給休暇を与える |
|
外国人への支援体制、 |
・支援は外国人が理解できる言語で行う ・面談を定期的に実施できる体制がある ・分野特有の基準に適合している |
受入れ機関を目指す際は、自社が基準から逸脱していないことを確認しましょう。
「1号特定技能外国人」への支援義務がある
受入れ企業は、1号特定技能外国人に対して支援計画を作成し、適切な支援を行うよう義務付けられています。支援計画の記載事項はおもに以下のとおりです。
・支援責任者の氏名、役職等
・登録支援機関(※登録支援機関に委託する場合のみ)
・支援に関する10項目
上記のうち、支援に関する10項目というのは、事前ガイダンスや出入国時の送迎、住居確保などの支援に関して定める項目のことです。
ただし、過去2年間に外国人が在籍していないと、そもそも自社での支援はできないため、外部の登録支援機関に委託する必要があります。登録支援機関に委託すれば、特定技能外国人の受け入れに向けて、支援計画策定のアドバイスなどをもらえます。
なお、2号特定技能外国人の支援に関しては義務付けられていません。
出入国在留管理庁への各種届出が必要になる
特定技能外国人を受け入れたあとも、出入国在留管理庁へのさまざまな届出を行う必要があります。例えば、雇用条件を変更した場合や特定技能外国人の受け入れが困難になった場合など、何らかの変更事項が発生すると、変更日から14日以内の届出が必要です。
万一、届け出の漏れがあると、罰金や過料の対象となる場合があるので注意しましょう。
対象分野によって所管省庁が異なる
特定産業分野は、運用方針や運用要領、試験に関する情報などが、各所管省庁などにより定められています。以下では、所管省庁ごとに対象分野を紹介するので、特定技能外国人の雇用を検討するうえで参考にしてみてください。
|
所管省庁 |
対象分野 |
|
厚生労働省 |
介護、ビルクリーニング |
|
経済産業省 |
工業製品製造業 |
|
国土交通省 |
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊 |
|
農林水産省 |
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
上表のとおり、各所管省庁によって対象分野は異なります。自社の事業が適合しているか知りたい場合は、各所管省庁のWebサイトで調べたり、直接問い合わせたりするとよいでしょう。
農業・漁業の分野以外は派遣形態で雇用できない
特定技能外国人を雇用するうえで、農業・漁業以外の分野は、原則として派遣形態での雇用ができない点に注意が必要です。その他の特定産業分野に関して認められているのは、フルタイムもしくは直接雇用のみとされています。
一方で農業・漁業に関しては、季節・地域による繁閑差を考慮して、派遣形態での雇用も可能です。ちなみに、農業分野での派遣雇用が認められているのは畜産農業全般で、漁業分野での派遣雇用が認められているのは、漁業・養殖業のみです。
特定技能外国人をアルバイト雇用できるかという点については、以下の記事をご参照ください。
特定技能外国人をアルバイトで雇用できる?外国人の雇用で確認すべき在留資格
特定技能所属機関(受入れ機関)をサポートする「登録支援機関」とは?
 特定技能外国人に対する支援は、受入れ機関が行うほか、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に、支援のすべてを任せることが可能です。
特定技能外国人に対する支援は、受入れ機関が行うほか、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に、支援のすべてを任せることが可能です。
前述のとおり、受入れ機関として外国人材を受け入れるには、過去2年間におよぶ外国人の在籍が求められるため、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は登録支援機関に委託することになります。
登録支援機関は、一定の基準を満たしている場合に、支援計画の作成や実施のサポートを行えます。出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に掲載されている登録支援機関は、2024年2月15日時点で9,468件です。
以降では、登録支援機関の具体的なサポート内容を紹介します。
登録支援機関によるサポート内容
登録支援機関は、受入れ機関が作成する支援計画について、その実作業を委託により引き受けることが可能です。
以下は、受入れ機関が行うおもな支援内容です。
・事前ガイダンス
・住宅確保の支援
・生活オリエンテーションの実施
・相談・苦情への対応
・日本語学習機会の提供
・出入国時の送迎
・公的手続きなどの同行
・日本人との交流促進
・定期面談・行政機関への通報
・転職支援
もともと特定技能所属機関の支援には、義務的なものと任意的なものがあると、法務省の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」に定められています。
例えば、「事前ガイダンス」の項目における入国手続きの説明などは、専門的な内容が含まれるため、自社ですべての支援を実施するのは難しいかもしれません。しかし、登録支援機関のサポートを受ければ、専門的な内容に関してもスムーズな進行が可能となり、自社の負担を減らせます。
また、外国人材が安心して日本で生活できるように、独自のサービスを提供している機関もあります。手厚いサービスのある機関を選ぶことで、外国人材を自社に定着させやすくなるでしょう。
特に、特定技能外国人を初めて受け入れる場合は、戸惑うことも多いかもしれません。しかし、登録支援機関によるサポートを受ければ、支援計画の策定に関するアドバイスをもらえたり、外国人が定着できるように支援を受けられたりするため、特定技能外国人のスムーズな受け入れを実現できます。
登録支援機関に関してさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
特定技能における登録支援機関とは?支援委託をおすすめする理由と選び方
特定技能外国人の雇用に関するご相談は「オノデラユーザーラン」へ
ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、特定技能外国人の人材紹介サービスを提供しており、特定技能外国人の受け入れに向けた支援をワンストップでサポートが可能です。
具体的には、企業様のニーズに適した人材を紹介できるほか、受け入れに際しての各種届出のサポート、入国前の支援計画の作成や事前ガイダンスの実施など、サービスが充実しています。これらのサービスにより、採用担当者の負担を抑えられるのがメリットです。
加えて、入国後の日本語学習機会の提供や日本人との交流促進、定期的な面談などもサポートできます。特定技能外国人の受け入れを検討しているという企業様は、一気通貫でのサービス提供が可能な当社へ、ぜひお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
まとめ
特定産業分野の人手不足に対応できる特定技能は、2号の対象分野が拡大したこともあり、今後さらなる需要増が見込まれます。ただし、企業が特定技能外国人を受け入れるには、支援計画の策定や在留資格の認定申請など、さまざまな手続きが必要です。
登録支援機関によるサポートをご検討される際には、ぜひ、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)へご相談ください。自社運営の海外現地アカデミーで、人材の募集から、独自教育した優秀な外国人材のご紹介、入国後の外国人材に必要な生活・教育にかかわる各種支援まで、ワンストップで実行します。そのため、受入れ企業様の手間を抑えた効率的な人材投入を実現できます。
特定技能外国人を雇用するか検討しているという採用担当の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説
- ARCHIVE