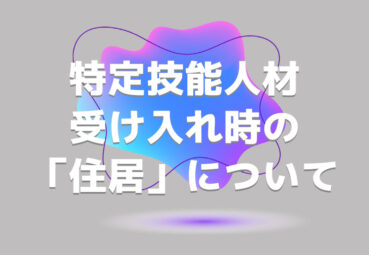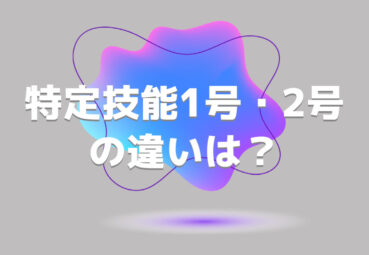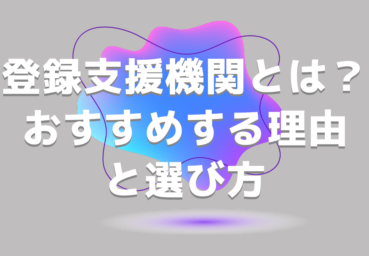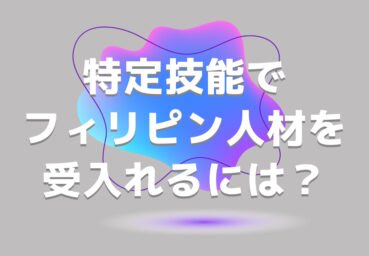特定技能関連

日本で働く外国人労働者の数は、年々増加しています。在留している外国人労働者を自社で受け入れたいと考えている方のなかには、彼らがどのような資格区分で働いているのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。
外国人労働者に求められる在留資格の一つが「特定技能」です。これまで12分野が対象となっていましたが、政府の決定で4分野が追加されたため、現在は16分野となっています。
また、既存の分野でもいくつか変更点が加わっているため、事前にチェックしておきたいところです。
この記事では、特定技能の基礎知識および2025年5月時点の最新情報を踏まえつつ、特定技能の分野・業種を解説します。併せて、特定技能の外国人労働者の受け入れ方法も、ぜひ参考にしてください。
目次
特定技能とは?
特定技能とは、国内で人材が不足する特定の産業分野で、外国人労働者を受け入れるための在留資格です。人手不足を解消し、企業経営を支えることを目的として、外国人労働者を雇用できるように2019年4月より始まりました。
特定技能を取得した外国人労働者は、単純労働をはじめとした幅広い業務に従事できます。ただし、分野ごとに従事できる職種が決まっているため、例えば介護の在留資格を持っていても、特定技能である建設の業務には従事できません。
創設当初は12分野で構成されていましたが、2024年3月29日の閣議決定にともない、特定技能に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されました。そのため、2025年5月現在は全16分野となっています。
さらに、既存分野の一部も内容が変更されているので、一緒に押さえておきましょう。こちらは「工業製品製造業」「造船・舶用工業」「飲食料品製造業」が対象です。
参照:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)|出入国在留管理庁
また、特定技能には、相当程度の知識や経験を持つ外国人が対象となる「特定技能1号」と、熟練した技能や専門的な知識を持つ外国人が対象の「特定技能2号」があります。特定技能2号資格に該当する外国人は在留期間の期限がなく、家族の帯同も可能です。
特定技能については、以下の記事でも詳しく解説しています。
外国人労働者の在留資格「特定技能」とは?1号と2号の対象分野などをわかりやすく解説
「特定技能2号」は2023年に対象分野が拡大
創設当初、特定技能1号では12の特定産業分野が対象となっていたのに対して、特定技能2号は「建設」「造船・舶用工業分野の溶接区分」のみが対象でした。しかし、2023年6月9日に、介護分野を除く11の分野が特定技能2号の対象となることが閣議決定され、同年8月31日からこの取り扱いが開始されています。
なお、介護分野では、すでに1号からの移行先となり得る専門的かつ技術的な分野の在留資格として「介護」があります。
また、先述したように閣議決定で新たに4分野が加わりましたが、これらの対象はすべて1号のみとなります。一方、変更があった分野に関しては、それぞれ対象が異なるため、あらかじめ注意が必要です。
2025年5月現在、一部の分野を除けば、原則として特定技能1号の在留資格を持つ外国人労働者の2号への移行が可能になります。各分野の1号から2号に移行するための試験は、既存の試験のほかに、各分野の所管省庁が試験実施要項を決定後、随時開始される予定です。
特定技能2号の対象分野を表形式でまとめたので、以下も併せてご確認ください。
| 分野 | 2号の対象可否 |
|
介護 |
1号のみ(在留資格「介護」あり) |
|
外食業 |
可 |
|
宿泊 |
可 |
|
飲食料品製造業 |
可 |
|
自動車整備 |
可 |
|
航空 |
可 |
|
農業 |
可 |
|
ビルクリーニング |
可 |
|
工業製品製造業 |
可 |
|
建設 |
可 |
|
造船・舶用工業 |
可 |
|
漁業 |
可 |
|
自動車運送業 |
1号のみ |
|
鉄道 |
1号のみ |
|
林業 |
1号のみ |
|
木材産業 |
1号のみ |
(2025年5月現在)
【職種一覧】特定技能の16分野・業種

具体的に、どのような仕事が特定技能に該当するのでしょうか。ここからは、特定技能に該当する16種類の分野・業種について、それぞれの概要や詳しい仕事内容を解説します。
2025年5月時点の最新情報も反映しているので、ぜひチェックしてください。
1.介護
介護は、介護施設で入所者の入浴や食事の介助、施設内でのレクリエーションの実施といった支援業務に従事するものです。
外国人が特定技能制度を用いて介護職につくには、事前に介護技能評価試験や介護日本語評価試験などの試験に合格する必要があります。
なお、2025年5月時点で判明している介護での労働者数(2024年10月末時点)は37,956人です。前年度の22,492人より大幅に増加していますが、これは日本における介護ニーズの増加や介護業界の人手不足といった事情が背景にあります。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
さらに、特定技能「介護」の試験は、日本のみならず海外でも積極的に行われており、現在はフィリピンなど計12ヵ国で受験可能です。合格者数も2024年6月末時点で87,371人に達しています。
また、これまで介護では「訪問系サービス」の業務が対象外となっていました。しかし、介護業界を取り巻く昨今の事情に鑑み、分野別運用方針が改正されたことにより、2025年4月21日から「訪問系サービス」への従事も認められています。
参照:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省
特定技能「介護」や訪問介護に関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。
特定技能「介護」とは?対応できる業務や取得方法、受け入れ側の注意点を解説
特定技能の訪問介護が解禁へ!現状や今後の動向、考えられる課題を解説
2.外食業
外食業では、料理店などでの調理や接客、店舗管理などの業務に従事させられます。外食業で受け入れできるのは、料理店や食堂のほか、喫茶店やファーストフード店、宅配専門店、仕出し料理店などです。
なお、外食業の労働者数(2024年10月末時点)は19,976人です。前年度の8,528人から2倍以上に増えていますが、これは外国人観光客の急増によるインバウンド需要の増加、新型コロナウイルス対策にともなう外出自粛の解消などが要因です。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
外食業の特定技能1号は合格者数が非常に多く、2024年6月末時点で71,615人となっています。
一方、2号の試験申し込みは企業からのみ可能であり、なおかつ受験要件としてマネジメント経験や店舗管理の補助経験が求められるなど、ハードルの高さゆえに合格者数も113人と少なめです。
なお、風営法の許可を受けた旅館・ホテルでの飲食提供全般に関する業務は現状認められていませんが、2025年3月11日の閣議決定により、これらも認可される方針に変わっています。
参照:特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)|出入国在留管理庁
特定技能「外食業」に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。
特定技能「外食業」とは?試験概要や取得・申請するための要件を解説
3.宿泊
宿泊では、ホテルや旅館といった宿泊施設にて、フロントをはじめとした接客業務、企画や広報、レストランサービスなどの業務に従事させることが可能です。
また、宿泊の関連業務の範囲であれば、掃除や配膳、ベッドメイキング、宿泊施設内の売店における販売なども対応可能業務に含まれます。これらは、あくまでも関連業務の場合に可能とされており、メイン業務としての従事はできない点に注意しましょう。
なお、宿泊の労働者数(2024年10月末時点)は1,137人です。前年度が542人だったので、2倍ほど増えています。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
また、宿泊の特定技能1号の合格者数は、2024年6月末時点で6,694人です。一方、2号はフロント業務・企画・広報・レストランサービスなど、さまざまな実務経験を要求されるため、合格者数はわずか4人でした。
特定技能「宿泊」に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。
特定技能「宿泊」で外国人材を雇用するには?対応可能業務や受け入れの流れ、注意点を解説
4.飲食料品製造業
飲食料品製造業では、酒類を除いた飲食料品の製造や加工に関する全般的な業務に従事させられます。この場合の飲食料品に含まれるのは、畜産食料品や冷凍食品、パン、清涼飲料水などです。
受け入れ企業は日本標準産業分類のうち、「食料品製造業」や「清涼飲料製造業」に該当しなければならない点に注意しましょう。
なお、飲食料品製造業の労働者数(2024年10月末時点)は58,361人です。前年度の42,062人から大きく増加しており、現状は最も外国人労働者数が多い分野となっています。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
特定技能1号の合格者数に関しても、2024年6月末時点で68,713人とトップクラスです。これまで技能実習生から1号に移行するケースが中心でしたが、今は試験を通じて直接取得するケースが増えています。
2号の合格者数も148人とそれなりに多いものの、1号に比べるとごく少数です。試験申し込みを企業経由でしか受け付けていないこと、受験要件に2年以上の実務経験を求められることなどが要因となります。
また、2024年3月29日の閣議決定により、特定技能外国人の受け入れが認められる事業所が追加されました。今後は食料品スーパーマーケットおよび総合スーパーマーケットにおけるて、食料品部門の惣菜などの製造ににでも従事できますがが可能です。、新規追加業種もすべて1号と2号の対象になります。
なお、業務区分は以前と同じく「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保」のみです。
特定技能「飲食料品製造業」に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。
特定技能「飲食料品製造業」を詳しく解説!雇用する際のポイントや受け入れ事例も
5.自動車整備
自動車整備では、中心業務として認められている自動車の日常点検整備や定期点検整備に従事させられます。また特定整備や、付随する電子制御装置の整備・板金塗装などの業務にも従事可能です。
自動車整備において外国人材には、日本国内の「3級自動車整備士」と同程度のスキルが求められる傾向にあります。
なお、自動車整備の労働者数(2024年10月末時点)は2,399人です。前年度は1,613人で、人数も増加率もそれほど多くありません。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
特定技能1号の合格者数は、2024年6月末時点で3,365人です。試験は海外でも開かれていますが、フィリピンとベトナムの2ヵ国のみとなります。
2号の合格者数はゼロですが、試験は頻繁に行われています。
特定技能「自動車整備」に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。
特定技能「自動車整備」とは?外国人を受け入れるメリットや業務内容、試験の概要も
6.航空
航空の業務区分は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2つに分かれています。
空港グランドハンドリングでは、航空機の地上走行支援業務や、乗客の手荷物・貨物取扱業務などに従事させることが可能です。一方の航空機整備では、エンジンオイルの確認をはじめとする、航空機の機体や装備品などの整備をおもに担わせられます。
航空の労働者数(2024年10月末時点)は928人であり、他分野に比べると少なめです。ただし、前年度は425人だったことから、増加率は悪くありません。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
特定技能1号の試験回数も比較的少ないものの、合格者数は2024年6月末時点で3,066人とまずまずです。海外では、フィリピンなど5ヵ国で開かれています。2号の試験は対象者がいなかったため、試験なしでした。
特定技能「航空」に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。
特定技能「航空」とは?対象業務や取得方法、受け入れ要件などを解説
7.農業
特定技能の農業において、外国人材は栽培管理を含む「耕種農業全般」や、飼養管理を含む「畜産農業全般」に従事可能です。
おもな業務内容は、耕種農業における栽培管理や農産物の選別・集出荷、畜産農業における飼養管理や畜産物の選別・集出荷です。他に、農畜産物を原料・材料とする製造や加工作業、農畜産物の運搬や陳列、販売、除雪作業などにも従事させられます。
なお、農業の労働者数(2024年10月末時点)は20,440人、前年度は14,616人です。増加率はそれほど高くないものの、母数が大きい分だけ人数も増えています。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
農業は特定技能1号の試験が海外12ヵ国で行われているため、2024年6月末時点の合格者数は56,555人と多い傾向にあります。2号の合格者数も188名と比較的多い状況です。
8.ビルクリーニング
ビルクリーニングとは、住宅を除いたさまざまな建物の内部を清掃する業務のことです。清掃場所や清掃部位、汚れの種類などに応じた適切な清掃方法や洗剤に関する知識が求められます。
ビルクリーニングの関連業務には、ベッドメイクを含む客室整備作業や資機材倉庫の整備作業が該当しているため、これらの業務を行わせることも可能です。ただし、メインの業務として想定されてはいません。
なお、ビルクリーニングの労働者数(2024年10月末時点)は4,128人です。前年度の2,194人から2倍近く増えていますが、人数自体はそれほど多くありません。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
特定技能1号の試験は海外でも7ヵ国で開かれており、2024年6月末時点の合格者数は9,101人でした。一方、2号は企業からのみ試験申し込みが可能で、現場管理の実務経験も2年以上必要といった要件もあり、合格者数はわずか3名です。
特定技能「ビルクリーニング」に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。
特定技能「ビルクリーニング」とは?業務内容・取得方法・採用時の注意点なども解説
9.工業製品製造業
工業製品製造業は、もともと3つに分類されていましたが、どの分野にも関連性があることから2022年に統合されました。また、2024年3月に分野名を「工業製品製造業分野」と変更し、新しい業種・業務区分を追加する閣議決定を行いました。どの分野・業種も日本経済に不可欠で需要が高い一方で、人手が不足しています。
素形材製造は、金属やプラスチックといった素材を加工し、組立産業に供給する職種です。そして、産業機械製造では産業用の機械を製造し、電気電子情報関連製造業ではおもに電子機器の機械加工や組み立てを行います。
なお、工業製品製造業の労働者数(2024年10月末時点)は30,206人です。主要な受け入れ分野ゆえに前年度も25,464人と多く、さらに人数が伸びています。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
一方、特定技能1号の合格者数は2024年6月末時点で947人と、労働者数に対して少ない傾向にあります。これは在留資格を技能実習から特定技能に切り替える方が大半で、試験を受ける方自体が少ないという事情によるものです。2号の合格者数は325人であり、既存の12分野中最多となっています。
また、2024年3月29日の閣議決定に基づき、工業製品製造業には新しく7つの業務区分が追加されています。
|
変更前 |
変更後 |
|
・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 |
・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・陶磁器製品製造 ・紡織製品製造 ・縫製 ・RPF製造 ・印刷・製本 |
また、既存の業務区分でも以下の事業所が追加されています。
・鉄鋼
・アルミサッシ
・プラスチック製品
・金属製品塗装
・こん包関連
新規追加業種に関しては、1号のみ受け入れ可能です。
10.建設
建設の業務は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つです。いずれの業務においても、指導者の指示や監督を受けつつ従事します。
土木業務は、土木施設の新設や維持、修繕に要するコンクリート圧送やとび職、建設機械施工などが該当します。建築業務に該当するのは、マンションや戸建て住宅の新築や改築、修繕などに要する建築大工や左官、内装仕上げなどです。
そしてライフライン・設備は、ガスや水道、電気通信などのライフラインや、重要設備の設置・変更・修理などに要する配管業務や電気工事などです。
建設の労働者数(2024年10月末時点)は20,972人で、既存の12分野中4番目に多い分野です。前年度も13,172人と比較的多く、人手不足を補うために外国人労働者の必要性が高まっている傾向にあります。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
また、建設も技能実習から特定技能にシフトする方が多いため、1号の合格者数は2024年6月末時点で1,853人と少なめです。一方、2号の合格者数は120人となっています。
特定技能「建設」に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。
特定技能「建設」とは?再編された区分や人材採用する側が満たすべき要件
11.造船・舶用工業
造船・舶用工業では、「造船」「舶用機械」「舶用電子電気機器」の3つに区分された業務にそれぞれ特定技能外国人を従事させることが可能です。
造船・舶用工業の特定技能資格を得るには、日本語試験以外に、各業務区分の造船・舶用工業分野特定技能1号試験への合格が必要です。
なお、造船・舶用工業の労働者数(2024年10月末時点)は7,616人です。前年度は5,415人なので、他分野ほど大きく増加していません。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
特定1号の合格者数は2024年6月末時点で214人であり、既存の12分野中最少です。1号の試験は集合形式で行われていますが、海外の実施国はフィリピンのみとなっています。
一方、2号の試験は「溶接・塗装・鉄工」の区分が実施されており、合格者数は85人です。取得するためには、造船・舶用工業における監督者の実務経験が2年以上求められます。
|
変更前 |
変更後 |
|
・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て |
・造船 ・船用機械 ・船用電気電子機器 |
また、作業範囲が拡大して各区分に新たな業務が追加されています。新規追加業種もすべて1号と2号の対象です。
|
業務区分 |
既存業務 |
追加業務 |
|
造船 |
・溶接 ・塗装 ・鉄工 |
・とび ・配管 ・船舶加工 |
|
船用機械 |
・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・溶接 ・仕上げ ・機械加工 |
・配管 ・鋳造 ・金属プレス加工 ・強化プラスチック成形 ・機械保全 ・舶用機械加工 |
|
船用電気電子機器 |
・機械加工 ・電気機器組立て |
・金属プレス加工 ・電子機器組立て ・プリント配線板製造 ・配管 ・機械保全 ・舶用電気電子機器加工 |
12.漁業
漁業は、業務区分が「漁業」と「養殖業」の2つに分かれています。
漁業では、水産動植物の探索や採捕、漁獲物の処理・保蔵、漁具や漁労機械の操作などを担わせることが可能です。一方の養殖業では、養殖している水産動植物の育成管理や収穫、養殖するために欠かせない資材の製作や補修、管理などを担います。
なお、漁業の労働者数(2024年10月末時点)は2,871人です。前年度は1,995人なので、他分野に比べて人数も増加率も低い傾向にあります。
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末現在)|厚生労働省
参照:「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末現在)|厚生労働省
また、特定技能1号の合格者数は2024年6月末時点で1,403人です。先述の労働者数と差がありますが、これは在留資格の切り替え(技能実習から特定技能)を選択した方が多いことを示唆しています。
2号は「日本語能力試験N3以上の合格」が申請要件とされており、前年度の合格者数はゼロでした。
13.自動車運送業
2024年から新たに追加された自動車運送業は、「バス運転者」「タクシー運転者」「トラック運転者」の3つの業務区分に分かれています。
おもな業務内容は、旅客や貨物を輸送するための「運航業務」です。バス・タクシーなら「接遇業務」も、トラックなら「荷役業務」も含まれます。
「車両の清掃」や「運行前後の準備・片付け」など、日本人従業員が通常担当する関連業務も付随的に従事可能です。一方、関連業務を専任的に従事することは認められていません。
物流需要の増加や2024年問題により、自動車運送業界はドライバー不足が深刻化しているため、外国人労働者のニーズが高まっている状況です。2024年から5年間にわたり、最大24,500人の受け入れが見込まれています。
また、自動車運送業の在留資格を取得するためには、業務で使う車種に対応した日本の運転免許が必要です。バス・タクシー運転手の場合、あらかじめ「新任運転者研修」も修了しなければなりません。
免許取得や研修受講をサポートするため、日本では「特定活動(特定自動車運送業準備)」の制度も始まっています。
14.鉄道
新規分野の鉄道は、業務区分が「運輸係員」「軌道整備」「電気設備整備」「車両製造」「車両整備」の5つに分類されており、それぞれ業務内容が大きく異なります。
例えば、軌道整備なら「レール交換作業」や「バラストを取り扱う作業」など、車両製造なら「素材加工」や「部品組立て」などに従事します。
各区分で指定された業務以外でも、日本人従業員が通常行う関連業務へは付随的に従事させることも可能です。「事務作業」や「作業場所の清掃」が該当しますが、関連業務だけ担うことはできません。
鉄道業界では、人材の高齢化や若年層の採用難といった問題を抱えているため、運行維持に向けて即戦力となる外国人労働者が求められている状況です。2024年から5年間にわたり、3,800人の受け入れが見込まれています。
15.林業
林業も新規分野ですが、業務区分は「育林、素材生産、林業種苗育成等」のみです。おもな業務内容は「苗木を植え、樹木を育てる作業」「丸太を生産する作業」になります。
「丸太の加工」「資材管理・運搬作業」など、日本人従業員が通常携わる関連業務を付随的に担うこともできますが、専任的な従事はできません。
森林資源の持続可能な利用が求められている一方、林業業界は高齢化と若年層の不足が進んでいるため、外国人労働者の需要が高まっている状況です。2024年から5年間で、最大1,000人の受け入れが見込まれています。
16.木材産業
新規分野の木材産業も、業務区分は「製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその付帯作業等」の一つだけです。業務内容は「製材業、合板製造業などに係る木材の加工等」となります。
「製品の検査」「出荷作業」など、日本人従業員が通常担当する関連業務にも従事させられますが、あくまで付随的でなければ認められません。
国内の木材・木製品製造業界では、人手不足が深刻化しているうえ、若年層の就業率も低いため、生産性向上に向けて外国人労働者を雇用する動きが活発です。2024年から5年間で、最大5,000人の受け入れが見込まれています。
「特定技能」で外国人労働者を受け入れる方法

企業や施設が特定技能に該当する分野・業種で外国人労働者を受け入れるためには、前提として、外国人材が特定技能の在留資格を取得している必要があります。
資格取得には、日本語試験や就労を予定している業務区分に対応した技能試験を受験し、いずれも合格しなければなりません。ただし、技能実習2号を良好に修了している外国人の場合は、これらの試験が免除されます。
さらに、人材を受け入れる企業側は、入国から帰国までのサポート、支援計画の作成が必要です。自社でサポートや計画の作成などの対応が難しい場合は、登録支援機関があり、サポートを受けることが可能ですので、検討してみてはいかがでしょうか。
ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)では、外国人労働者の入国前の支援計画をはじめ、入国時の公的手続きなどの同行やハウジングなど、ワンストップでご利用いただけるサービスを提供しています。また、OUR BLOOMING ACADEMY(自社アカデミー)で専門教育や育成を施した特定技能外国人の紹介も行っています。
さらには、外国人労働者の定着を目的に独自の生活・学習支援サービスも実施しているため、初めて特定技能外国人を受け入れるという企業様も安心していただけるでしょう。特定技能によって外国人労働者を受け入れたいと考えている方は、ぜひご相談ください。
まとめ
国内のさまざまな分野・業種において発生している人手不足を背景に、特定技能を有する外国人労働者の需要は高まると予想されます。特定技能を取得している外国人労働者は幅広い業務に従事できるので、企業にとって大きな戦力となり得るでしょう。
また、政府の決定によって特定技能は12分野から16分野へ拡大し、既存の分野でも変更点が加わっているため、最新動向をきちんと把握しておきたいところです。
特定技能を有する外国人労働者の受け入れを検討しているものの、受け入れに際してサポートや各種手続き、支援計画の作成に不安があるという場合は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にお任せください。アジアの若く、優秀な人材が企業様で存分に活躍できるよう、さまざまなサービス・サポートを提供します。
お問い合わせはこちら
- お役立ち情報一覧
-
前のページへ
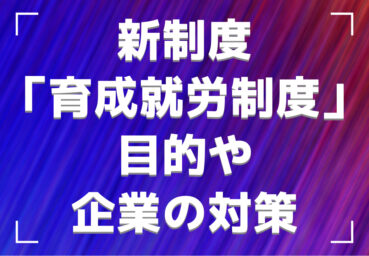 【技能実習生受入れ制度が廃止】新制度「育成就労制度」の目的や企業の対策も解説
【技能実習生受入れ制度が廃止】新制度「育成就労制度」の目的や企業の対策も解説
-
次のページへ
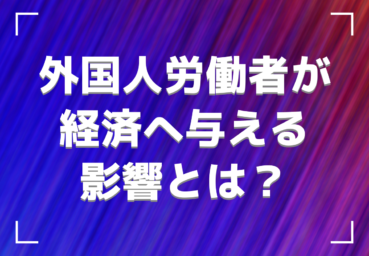 外国人労働者の増加が経済へ与える影響とは?特定技能制度や技能実習制度の見直しも解説
外国人労働者の増加が経済へ与える影響とは?特定技能制度や技能実習制度の見直しも解説
2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説
- ARCHIVE
-
-
- 2025年
-
- 2020年
-