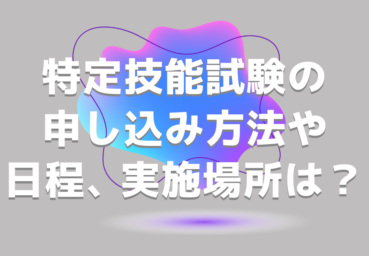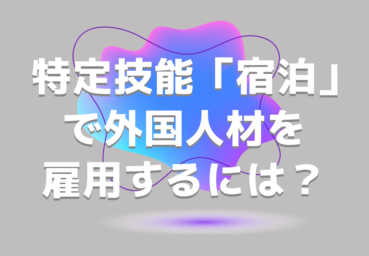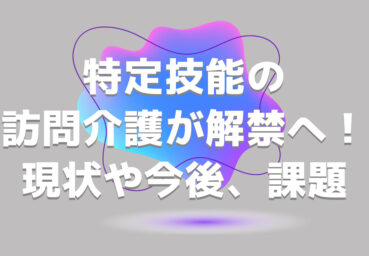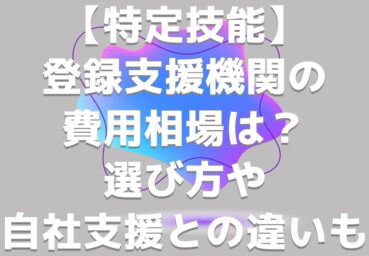特定技能関連
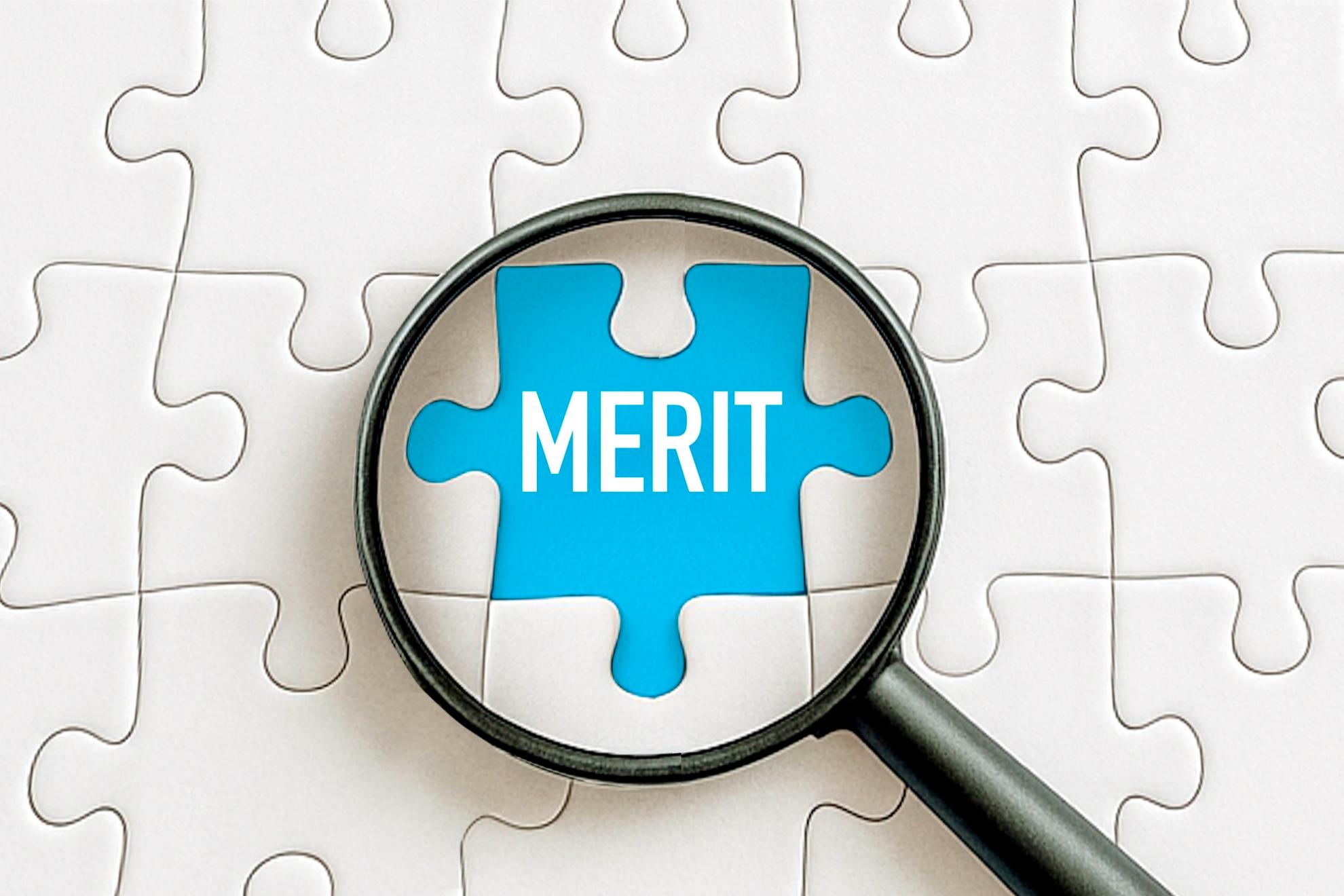
在留資格「特定技能」を取得した外国人材の受け入れは、人手不足に悩む企業にとって有効な手段です。職場のグローバル化や活性化など、副次的なメリットもあります。
この記事では、特定技能制度の基礎知識とともに、特定技能外国人を採用するメリットや注意点を解説します。特定技能外国人の受け入れに成功した企業事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
在留資格「特定技能」とは?
「特定技能」とは、人手不足に悩む特定産業分野において、人材を確保することを目的とした在留資格です。
2019年4月に創設された特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つのカテゴリに分かれています。特定技能1号よりも2号のほうが熟練した専門知識や技能を求められるのが特徴で、在留期間や対象分野、家族帯同の可否などにも違いがあります。
なお、特定技能制度全体の対象分野は、2025年9月時点で全16分野です。
在留資格「特定技能」に関する基礎知識や、特定技能1号と2号の違い、特定技能制度の対象分野について詳しくは、以下の各記事をご覧ください。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説
2025年最新|特定技能の16分野・業種の職種一覧と現状を解説!
特定技能制度と技能実習制度(育成就労制度)の違い
特定技能と混同されやすい制度に、「外国人技能実習制度」があります。技能実習制度は、開発途上国などの外国人に日本の技能・技術・知識を移転し、母国で活躍できる人材を育成にすることによる国際貢献を目的で創設されたものです。
技能実習と特定技能の7つの違いとは?どちらの制度にすべきか迷ったときの考え方も
しかし、「国際貢献」という制度本来の目的に反して、「労働力確保」のために利用されている現状が問題視されていました。このような実態を踏まえ、技能実習制度を発展的に解消し、新たに「育成就労制度」を創設することが決まっています。
特定技能制度と育成就労制度は、人手不足に対応するための制度であるという点で共通しています。ただし、特定技能制度では即戦力となる外国人材の受け入れを想定している一方で、育成就労制度では入国時点での専門性は求められないのが大きな違いです。
育成就労制度について詳しく知りたい方は、以下の各記事を参考にしてください。
【技能実習生受入れ制度が廃止】新制度「育成就労制度」の目的や企業の対策も解説
【最新動向】育成就労制度とは?基本的な方針・ポイント・問題点をわかりやすく解説
特定技能制度で外国人労働者を採用するメリット

ここでは、企業が特定技能外国人を受け入れるメリットを解説します。
人手不足の解消に繋がる
特定技能制度の目的からもわかるとおり、特定技能外国人の受け入れは人手不足の解消に有効な手段です。
特定技能外国人は、原則として「週5日以上かつ年間217日以上」かつ「週30時間以上」の、フルタイムでの勤務が求められています。そのため、企業は日本人労働者と同等に仕事を与えられます。
また、介護分野と建設分野を除き、企業ごとの特定技能外国人の受け入れ人数に上限は設けられていません。状況に応じて、多くの外国人材を受け入れることも可能です。
なお、日本で労働者不足が進行している背景や、特定技能外国人の受け入れ人数については、以下の各記事で解説しています。
日本で労働者不足が進行している背景とは?企業への影響や解消方法も詳しく解説
【2024最新】特定技能外国人の受け入れ人数に上限はある?技能実習との違いなども解説
即戦力となる人材を確保できる
外国人材が特定技能制度で就労するためには、「技能試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。つまり、特定技能外国人は、相当程度の技能水準と日本語能力水準を満たしているといえます。
企業は受け入れにあたって初歩的な教育をする必要がなく、特定技能外国人は即戦力となってくれるでしょう。人材育成のための手間やコストを抑えられ、生産性の向上が期待できます。
特定技能制度の試験については、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
特定技能制度の試験とは?即戦力の外国人を受け入れるための基礎知識
短期間での離職リスクを抑えられる
特定技能外国人は、転職することも可能です。しかし、異なる産業分野へ転職する場合は、新たに試験に合格しなければなりません。
また、在留資格変更許可申請が必要になり、その間は収入が得られないなど外国人材にとって異なる産業分野への転職ハードルは高い傾向があります。
さらに、特定技能1号の在留期間の上限は5年ですが、特定技能2号に移行することで在留更新の回数上限がなくなります。このような理由により、短期間での離職リスクを抑えた採用を実現しやすいのがメリットです。
特定技能外国人は転職できる?要件・手続きやリスク、企業が取るべき対策を解説
職場のグローバル化が促進される
特定技能外国人を受け入れることで、異なる国の言語や文化を共有でき、職場のグローバル化が促進されます。その結果、海外での新規顧客獲得や海外取引先との関係性構築などの場面において、国際的な競争力が高まるでしょう。
現在は国内市場に留まっている企業でも、将来的に海外への事業展開の可能性がある場合は、外国人材の知見やスキルを活かすのが有効です。
以下の記事では、企業がグローバル化に取り組むメリットや人材戦略などについて解説しています。
企業のグローバル化に必要な人材戦略とは?外国人雇用のメリットやポイントも解説
社内活性化や業務見直しのきっかけとなる
あえて日本で働くことを選んだ特定技能外国人は、自分の技能を活かしたいと意欲的な方が多くいます。高い志を持って働く姿や外国人材ならではの新たな視点・発想は、日本人労働者にとって良い刺激となり、職場が活性化するきっかけとなるでしょう。
また、特定技能外国人を受け入れるにあたり、自社の作業工程をあらためてチェックする必要があります。慣習的に進めていた点を見直し、合理化・効率化を図ることができれば、既存の従業員も特定技能外国人もより働きやすい職場になります。
特定技能外国人を受け入れる際の注意点・課題
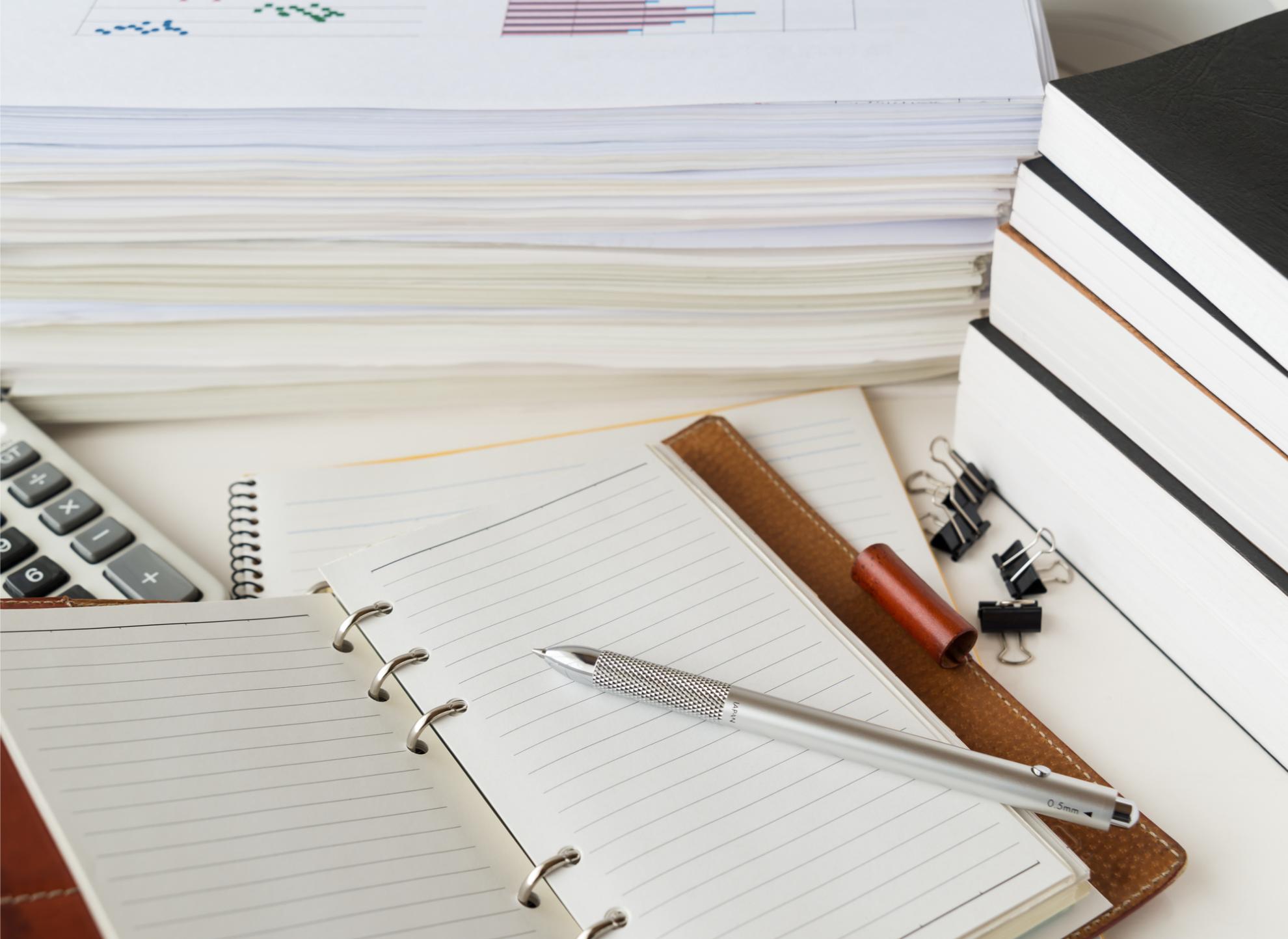
特定技能外国人の受け入れは多くのメリットがある一方で、注意点や課題も存在します。ここでは、企業が特定技能外国人を受け入れる際の注意点や課題を、解決策などとともに見てみましょう。
義務的支援を行う必要がある
1号特定技能外国人の受入れ企業は、外国人材が日本で安定的かつスムーズに活動できるように「義務的支援」をしなければなりません。義務的支援の内容は、以下の10項目です。
- 1.事前ガイダンス
- 2.出入国する際の送迎
- 3.住居確保・生活に必要な契約支援
- 4.生活オリエンテーション
- 5.公的手続き等への同行
- 6.日本語学習の機会の提供
- 7.相談・苦情への対応
- 8.日本人との交流促進
- 9.転職支援(人員整理等の場合)
- 10. 定期的な面談・行政機関への通報
出典:出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
このように、事前ガイダンスや生活オリエンテーションといった受け入れ開始時の支援だけでなく、受け入れ後の各種サポートも重要となります。
特定技能外国人を支援する「生活オリエンテーション」とは?時間や内容について解説
特定技能外国人の住居に関する条件とは?住宅確保の背景や注意点も解説
ただし、義務的支援に関する業務は、「登録支援機関」に10項目全部または一部を委託することも可能です。特定技能外国人の支援体制を整える余裕がない企業は、登録支援機関のサポートを受けるとよいでしょう。登録支援機関について詳しくは、以下の記事で解説しています。
特定技能における登録支援機関とは?支援委託をおすすめする理由と選び方
手続きが負担になる場合がある
特定技能制度は、状況に合わせて変化しています。最新の動向も含めて制度を理解しなければならず、特に特定技能外国人を初めて受け入れる企業にとってはハードルが高いかもしれません。
特定技能外国人を受け入れることを決めたら、先述した義務的支援に限らず、面接や雇用契約書の作成、出入国在留管理庁への申請・届出など、さまざまな手続きも発生します。ケースによっては、外国人材の母国機関とのやり取りが必要になることもあるでしょう。
こうした負担を減らしたい場合も、登録支援機関を活用するのが有効です。
外国人採用の面接で使える質問例!事前準備や注意点も企業向けに解説
【担当者必読】特定技能の定期報告とは?必要書類や届出方法をまとめて解説
異文化コミュニケーションが難しい
言語や文化が異なる特定技能外国人の受け入れは、職場のグローバル化に繋がる一方で、コミュニケーションの難しさが課題となります。
外国人材が一定の日本語能力水準を満たしているとはいえ、企業側も対策が必要です。対策を取らないままでは、業務の効率低下やトラブルを引き起こしたり、外国人材が不安や不満を抱える原因となったりします。
異文化コミュニケーションを円滑に行うためには、企業の価値観を押し付けることなく、外国人材の背景や日本語能力に合わせたやり取りを心がけることなどが大切です。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
外国人材との異文化コミュニケーションで大切なことは?重要な理由や交流のコツも解説
日本人と同等の雇用条件が求められる
フルタイムでの勤務が求められる特定技能外国人は、正社員として直接雇用するのが原則です。
そのうえで、日本人労働者と報酬額が同等以上であること、所定労働時間が同等であることが企業に求められます。「特定技能外国人を採用すれば、安価に労働力を確保できる」といった誤解に注意が必要です。
また、特定技能外国人が一時帰国を希望した際には、必要な有給休暇を取得できるよう配慮しなければなりません。このような点を理解したうえで、正当な雇用契約を結びましょう。
特定技能外国人を採用するなら登録支援機関のサポートを活用!

登録支援機関のサポートを活用すれば、特定技能外国人を初めて受け入れる場合でも、前章で紹介した課題を解決しつつスムーズな対応ができます。
登録支援機関である「ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)」なら、外国人材の受け入れに関する一気通貫のサービス(OURストレートスルー)を提供可能です。具体的には、海外にある自社無償教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMY」にて特定技能外国人の教育や育成を行い、企業様のニーズに沿った人材を紹介しています。
また、特定技能1号の義務的支援の内容を含めた、以下のようなサービスも実施しています。
- ・支援計画の策定
- ・事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施
- ・日本語学習機会の提供
- ・やさしい日本語&コミュニケーション講座の開催(受入れ企業様向け)
- ・各種申請手続きのサポート など
-
詳しくは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
-
特定技能外国人の受け入れに成功した企業事例

-
最後に、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)を介した特定技能外国人の受け入れについて、成功した企業事例を紹介します。
なお、今回紹介するもの以外にもさまざまな事例があるので、ぜひ事例紹介ページもご覧ください。
事例紹介ページはこちら -
事例1.特定技能「介護」の導入企業
-
「特別養護老人ホーム 南風苑」および「介護老人保健施設 ほんごう苑」では、フィリピンの特定技能「介護」の人材を4名ずつ採用しています(2024年10月時点)。人手不足に悩むなか、安定した労働力の確保のために外国人材の受け入れを決意したのがきっかけです。
事前に専門教育をしっかりと受けた質の高い外国人材をOURが紹介したことで、受け入れ側の負担が減り、期待以上の戦力になりました。一緒に働く日本人職員からの評価も高く、特定技能外国人の受け入れはうまくいったと実感しています。
事例の詳細はこちら
特定技能「介護」について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
-
事例2.特定技能「外食」の導入企業
-
「医療法人誠和会 正田病院」では、ラオスの特定技能「外食業」の人材を2名採用しています(2024年11月時点)。初めての外国人材の採用だったものの、OURのフォローにより問題なく進められました。
受け入れ前にラオスの方の人柄についても職場内で共有し、コミュニケーションを取る際に活かしています。現在では、外国人材は独り立ちできるようになり、責任を持って仕事をしてくれています。
事例の詳細はこちら
特定技能「外食業」について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
-
事例3.特定技能「外食」・「飲食料品製造」の導入企業
-
「株式会社MOTHERS」では、フィリピンの特定技能「外食業」の人材8名、インドネシアの特定技能「飲食料品製造業」の人材4名と、計12名を採用しています(2023年11月時点)。真面目な人材ばかりで、働きたい意欲を持って日々の業務に取り組んでくれています。
また、外国人材を受け入れたことで、英語版のマニュアル作成や指示の伝え方の工夫など、現場教育の改善が進みました。スタッフ同士の会話も活発になり、店舗全体の雰囲気がより明るく活気付くという変化がありました。
事例の詳細はこちら
特定技能「飲食料品製造業」について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
-
まとめ
-
即戦力となる特定技能外国人を採用できれば、人手不足の解消に繋がるのはもちろんのこと、職場のグローバル化や活性化の促進などのメリットも得られます。
ただし、特定技能外国人を受け入れる際には、複雑な制度や手続きを理解したうえで、義務的支援を行ったり、異文化コミュニケーションに対応したりする必要があります。
こうした負担を軽減するには、登録支援機関のサポートを活用するのが有効です。特定技能外国人の採用を検討している方は、ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)までぜひお気軽にご相談ください。
-
お問い合わせはこちら
- お役立ち情報一覧
-
前のページへ
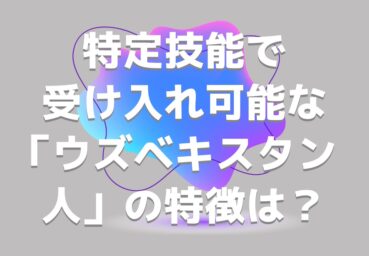 特定技能で受け入れ可能な「ウズベキスタン人」の特徴は?採用時の流れやポイント
特定技能で受け入れ可能な「ウズベキスタン人」の特徴は?採用時の流れやポイント
-
次のページへ
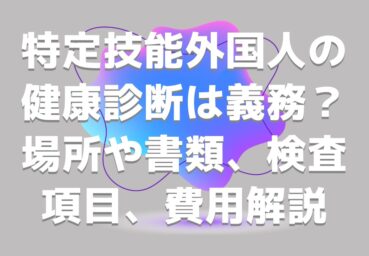 特定技能外国人の健康診断は義務?実施場所・必要書類・検査項目・費用も詳しく解説
特定技能外国人の健康診断は義務?実施場所・必要書類・検査項目・費用も詳しく解説
2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説
- ARCHIVE
-
-
- 2020年