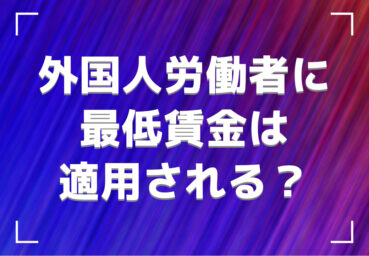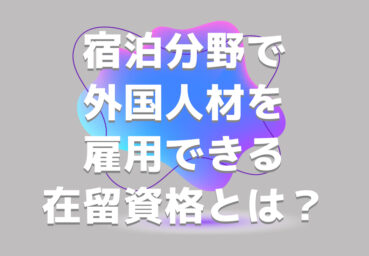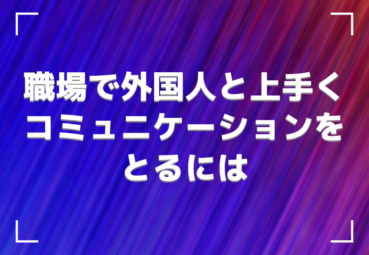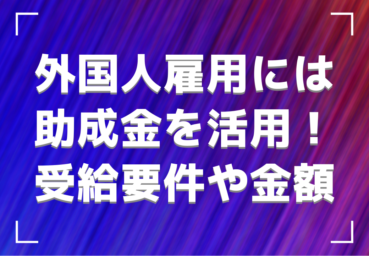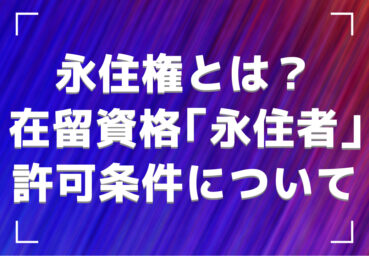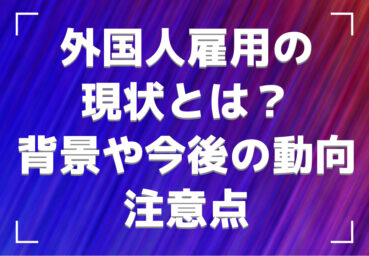その他
日本でも受け入れを拡大している外国人労働者は、人手不足の解消をはじめとしたさまざまなメリットをもたらす一方で、適切に活用しなければトラブルに発展する恐れもあります。
外国人労働者を受け入れるためには、メリットに目を向けるだけでなく、具体的な制度や法令関係の理解や遵守、外国人労働者の実態、トラブルの事例や対策などを知っておくことが重要です。
この記事では、外国人労働者の定義や在留資格、外国人労働者の現状、よくあるトラブルやその対策、技能実習から育成就労への制度の移り変わりなどについて、わかりやすく解説します。

外国人労働者とは
まずは、外国人労働者の定義と、在留資格と就労の関係について、わかりやすく解説します。
外国人労働者の定義
外国人労働者とは、日本国籍をもたずに日本で働く外国人の労働者のことです。日本では、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で定められている在留資格の範囲内において、外国人の就労活動が認められています。在留資格をもたずに働いている場合は不法就労者となり、雇用した企業は入管法違反で罰則を受けてしまいます。
在留資格と就労の関係
在留資格とは、外国人が日本に在留して活動を行うために必要な資格で、目的別にさまざまな種類があります。在留資格の種類によって、在留期間や就労の可否などに違いがあるため、企業の採用担当者も正しい知識が必要です。
就労可能な在留資格にもさまざまな種類があり、資格によって就労可能な業種や在留期間が異なります。代表的な在留資格には、介護・外食・宿泊・ビルクリーニングなど特定分野で即戦力となる外国人を対象とした「特定技能」や、技能・技術・知識の習得を目的とする「技能実習」などがあります。
外国人労働者の現状

日本における外国人労働者数の推移や主要産業での受け入れ状況、依存度の高い業界について、それぞれ解説します。
外国人労働者数の増加
厚生労働省の調査によると、2024年10月末時点の外国人労働者数は約230万人で、前年と比べて約25万人増加しています。届出が義務化された2007年以降、過去最多を更新しており、外国人労働者数は増加傾向にあることがわかります。
また、外国人を雇用する事業所数は約34万所で、前年と比べて約2万所増加し、外国人労働者数と同様に過去最多を更新しました。
国籍別では、最も多いのがベトナムで約57万人(全体の24.8%)、2位が中国で約40万人(全体の17.8%)、3位がフィリピンで約24万人(全体の10.7%)となっています。
在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最多で約71万人、次いで「身分に基づく在留資格」が約62万人、「技能実習」が約47万人、「資格外活動」が約39万人、「特定活動」が約8万人となっており、すべての在留資格が前年と比べて増加している結果となりました。
出典:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」
主要産業での受け入れ状況
外国人労働者を多く受け入れている産業は製造業で、外国人労働者全体の26.0%が該当しています。次に多いのがサービス業で、全体の15.4%を占めています。ここでいうサービス業は、宿泊業・飲食サービス業を除く労働者派遣業などの幅広い業種のことです。続いて卸売業・小売業が13.0%、宿泊業・飲食サービス業が11.9%、建設業が7.7%となっています。
出典:厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点)」
依存度の高い業界
厚生労働省の調査では、2023年から2024年にかけて外国人雇用事業所数が最も増加したのは建設業で、1年間で13.7%も増加しています。若年層の入職者減少と高齢化が進み、人手不足の問題が深刻化している建設業では、外国人労働者への依存度が増しているといえるでしょう。
また、医療・福祉分野や卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業についても、外国人雇用事業所数の増加率が高くなっています。
出典:厚生労働省「別添3「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点)」
外国人労働者問題でよくあるトラブル
外国人労働者の活用はさまざまなメリットがある反面、知らないうちに違法行為となることや、トラブルに発展しやすい要素もあるため注意が必要です。ここでは、現場でよくある7つのトラブルについて、トラブルの内容や注意点などを解説します。
問題1:低賃金・賃金未払い
外国人労働者に対して「最低賃金を下回る賃金しか支払われない」「残業代が未払い」など、賃金に関するトラブルが発生するケースがあります。また、低賃金を理由に技能実習生が失踪するケースも少なくありません。
企業には、労働基準法に基づいた賃金を適正に支払うことが求められます。また、違法な賃金未払いは、企業側が罰金や懲役といった罰則を受ける可能性があるのはもちろん、社会的な信用を失うことにもつながります。
問題2:過酷な労働環境
人手不足の業種では長時間労働や重労働が常態化しているケースも多く、外国人労働者にとって業務負担が過重になっている場合があります。また、休憩や休日が十分に取れないなど、安全衛生管理の不備も問題となっています。
外国人労働者であっても、日本で働いているのであれば日本人と同様に労働基準法が適用されます。法定労働時間を超える長時間労働の強制などは、決して許されません。法令遵守はもちろん、定期面談を実施するなどコミュニケーションの機会を確保し、長時間労働や過重な業務負担の解消に務めることが重要です。
問題3:コミュニケーションの障害
外国人労働者と日本人従業員との間に言葉の壁が生じ、日本語のニュアンスや曖昧な表現が伝わらずにトラブルに発展するケースがあります。特に業務内容や安全に関する情報が正確に伝わらないと、重大なミスや事故に繋がりかねません。
具体的には、「日本語での業務指示が正しく伝わらずにミスが発生する」「時間の感覚や上下関係など、文化の違いによって摩擦が生じる」「困りごとをうまく伝えられずに問題が深刻化してしまう」などの問題が発生する恐れがあります。
外国人労働者向けに、図・写真・動画を活用した視覚的な補助やマニュアルの多言語化を進めたり、日本人従業員向けに異文化理解研修を実施したりするなどの工夫が必要です。
問題4: 就労制限(在留資格の壁)
在留資格によって活動範囲や労働時間などの就労制限があるため、違反することで企業側は不法就労助長罪、労働者側は不法就労罪で罰則対象となり、退去強制となる恐れもあります。たとえば、就労不可の在留資格者を就労させたり、許可された範囲外の業務に従事させたりすると、違反となってしまいます。
企業は外国人労働者の在留資格を正確に把握し、在留期間や資格外活動許可の有無、活動範囲を必ず確認することが重要です。
問題5: 昇給・昇進制度が文化に合わない
日本特有の昇進制度や企業文化が合わずにトラブルに発展するケースもあります。たとえば、「成果を出しても年齢や勤続年数が重視されて昇進が遅い」のような年功序列の文化に対する不満、「情意評価」や「空気を読む」といった曖昧な基準が理解しづらいなどの例が挙げられます。
成果をあげた分だけすぐに報酬が増えるような「成果主義」を期待することが多い外国人に対し、プロセスを重視し、評価から賃金反映までに時間がかかる日本の文化は、不満に感じる場合もあるでしょう。
企業としては、評価制度を透明化したり、キャリアパスを明確に示したりするなどの工夫が必要です。評価の説明や指導については、個別の面談の場を設けて丁寧に行うことも大切です。
問題6: 地域コミュニティとの溝
外国人労働者は、言語によるコミュニケーションがうまくいかないことで地域活動に参加できず、孤立してしまうこともあります。また、地域住民側も、地域に外国人が増えることによる不安などから、誤解や差別的な態度につながることもあるでしょう。
地域住民と外国人労働者が共に支え合う関係になれるよう、企業による地域マナー教育や、自治体や支援機関による交流イベントを行うなど、企業と地域が協力して相互理解を深めていくことが大切です。
問題7: 不慣れな生活環境によるトラブル
外国人労働者は、文化や言語の違いによって、ゴミ出しルールや生活音の大きさ、食事のマナーなどでトラブルに発展するケースがあります。また、言語の壁や文化の違いで賃貸契約や住所登録がスムーズに進まなかったり、水道・ガス・電気などのライフライン契約が複雑で故障時の対応が遅れてしまったりすることもあるでしょう。
企業側は、社宅や寮の提供、ライフラインの契約代行、住民票の作成などの手続きの支援などのサポート体制を整えておくことが大切です。また、地域のゴミ出しのルールや騒音問題などのマナーを説明したり、緊急時の連絡体制を整備したりしておくことも必要です。
外国人労働者問題改善のための対策
外国人労働者問題を改善するためには、「日本人と同等の待遇・労働条件の整備」「求人票・雇用契約内容の明確化」「採用担当者による制度理解と労務管理の徹底」「受け入れ体制(生活・職場環境)の強化」などの対応が求められます。それぞれの対策について解説します。
日本人と同等の待遇・労働条件の整備
日本国内における外国人労働者の待遇・労働条件は、日本人と同等の基準を満たすことが法律で義務付けられています。企業は同一労働同一賃金の原則に基づいて、同じ業務内容であれば国籍や雇用形態に関係なく日本人と同等の賃金・待遇を確保しなければなりません。
重要なのは、「待遇差に合理的な理由があるかどうか」がポイントです。仕事の責任や能力、経験の違いに応じた待遇差は認められるものの、「外国人だから」という理由は差別にあたるため、絶対にあってはなりません。
また、日本人労働者と同様に最低賃金法が適用されるため、日本人と同等以上の給与・待遇を保証する必要があります。特に特定技能では、即戦力として同等以上の待遇が求められます。適切な待遇改善や労働条件の整備は、優秀な人材の確保と定着を促すためにも重要な課題のひとつといえるでしょう。
求人票・雇用契約内容の明確化
法的なトラブル回避や適正な雇用管理のためには、求人票や雇用契約内容の明確化は必要不可欠です。2024年4月に改正された職業安定法施行規則でも、労働条件の明示義務が強化されています。具体的には、募集する労働者の労働条件に加えて、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業の場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」の明示が必要です。
雇用契約書には、在留資格と業務が合致していることや、具体的な就業場所や業務内容、賃金の金額と支払方法、休日・休暇、退職・解雇に関する事項などについて詳細に明示する必要があります。
日本語のみの契約書は、内容を理解していないとして無効になるリスクがあるため、母国語併記の契約書を使用するとよいでしょう。「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、すべての条件を書面で明確に提示することも大切です。
採用担当者による制度理解と労務管理の徹底
採用担当者が入管法や労働基準法などの関連制度を正しく理解し、労務管理を徹底することは、企業の法的なリスク回避と人材の定着には欠かせない要素です。
採用担当者が理解しておくべき基本的な内容として、まずは在留資格や在留カードを正しくチェックすることが挙げられます。在留資格については、対象者が就労可能な在留資格をもっているか、活動範囲と業務内容が合っているかを確認します。在留カードについては、有効期限や資格外活動許可の有無を確認し、不法滞在や許可範囲外の就労を防ぎましょう。
また、外国人労働者に対しても日本人と同様に労働基準法等の労働関係法令が適用されるため、もちろん差別的な待遇も禁止されています。不法就労助長罪などのリスクを避け、外国人労働者を適正に雇用するためにも、制度を正しく理解して、労務管理を徹底することが大切です。
受け入れ体制(生活・職場環境)の強化
外国人労働者がスムーズに生活環境や職場関係に適応するためには、受け入れ体制を強化することが重要です。生活面では、まずは行政手続きに関するサポート体制を構築することが求められます。また、外国人向けの生活ガイドブックやポータルサイトの活用、情報提供、地域での交流機会の提供など、地域との連携も大切です。
職場環境においては、まずは言語サポート体制を整える必要があります。たとえば、多言語対応コミュニケーションツールの導入や業務に必要な専門用語の研修など、言葉の壁をなくす工夫を取り入れましょう。
日本の職場ルールに関するオリエンテーションや異文化理解研修、交流イベントの実施など、外国人労働者と日本人従業員が相互理解を深める機会を積極的に設けることも大切です。また、困ったときに頼れる相談窓口の設置やメンタルヘルスサポートの提供も重要です。
外国人労働者を受け入れるメリット

外国人労働者を受け入れる主なメリットには、「人手不足の解消」「若手人材の獲得」「組織の活性化」「多様な視点・創造性の導入」「国際化の推進」などがあります。それぞれのメリットについて解説します。
人手不足の解消
外国人労働者の受け入れは、深刻な人手不足の解消に大きく貢献します。少子高齢化によって労働人口が減少するなかで、外国人材が豊富な労働力を提供することは、事業の維持・安定運営を支える大きな力となるでしょう。日本人労働者だけでは不足する分野で外国人材を対象に加えることで、採用できる人材の選択肢が広がります。
特に、在留資格の「特定技能」は、人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人材を受け入れるための制度であるため、計画的に労働力を補完することに繋がり、人手不足の解消と同時に企業成長と競争力強化に繋げることも可能です。特定技能2号は、在留更新の上限がなく、長期就労につながりやすく、要件を満たせば家族帯同も可能になるため、日本の労働力人口減少対策にも大きく貢献するでしょう。
また、外国人労働者によって不足する人員を補うことで、日本人従業員の長時間労働の改善にも繋がります。本来の業務や管理業務に集中できるようになることで、従業員の満足度が高まり、従業員の離職を防ぎ、定着率の向上にも寄与するでしょう。定着率の向上は、人手不足の問題の解消にも繋がります。
若手人材の獲得
外国人労働者のなかでも、特に若手人材の獲得は、日本国内の若年層不足を補うことに大きく貢献します。厚生労働省の調査によると、2024年の外国人労働者の平均年齢は32.8歳でした。外国人労働者は若年層が多いため、若手の外国人労働者を獲得することは、長期的な人材確保にも繋がるといえるでしょう。
また、日本で働く意欲が高い若手人材も多く、日本語やスキルの習得に積極的で、業務改善に貢献するようなケースもあります。優秀な若手人材を獲得するためには、競争力のある報酬設定や、日本語教育や生活支援など受け入れ体制の整備、将来を見据えたキャリア形成支援などが必要です。
組織の活性化
異なる文化的背景や価値観をもつ人材がチームに加わることで、従来の日本企業にはない柔軟な思考が生まれ、組織の活性化に繋がります。異なる価値観や文化を互いに尊重し合う組織風土であれば、外国人労働者を受け入れることで社内に活気をもたらし、日本人従業員の成長や新しいビジネスチャンスに繋がることも期待できるでしょう。
また、海外の商習慣や言語を理解している人材が海外進出の橋渡し役となったり、インバウンド需要への対応や海外企業との連携強化に貢献したりするなど、グローバル対応力を強化することにも繋がります。
さらに、日本人従業員にとっても、異文化理解が深まったり、コミュニケーション能力や柔軟性の向上につながったりと、成長に繋がる機会になるでしょう。
多様な視点・創造性の導入
外国人労働者を受け入れることで、多様な視点から新しい発想やアイデアが生まれやすくなり、ビジネスの発展やイノベーションの促進にも繋がるでしょう。
たとえば、日本人従業員とは異なるバックグラウンドをもつ外国籍労働者が日本特有の考え方や文化に疑問を呈することで、新しい視点で業務を見直すことに繋がります。多様な視点によって業務が見直されることによって、固定観念にとらわれない独自のアイデアが生まれることもあるでしょう。
さらに、文化や背景が異なるメンバーで構成されたチームは、複雑な課題に対して多角的なアプローチが可能です。業務を進めるなかでさまざまな課題に直面しても、迅速かつ柔軟な問題解決が可能になり、問題解決能力の向上にも繋がるでしょう。
国際化の推進
外国人視点をもつことは、インバウンド需要や海外市場のニーズを正確に捉えることにも寄与し、新しいマーケティング戦略や商品開発にも繋がります。企業として多様な視点や創造性が広がることで、国際的な競争力の向上も期待できるでしょう。
また、外国人労働者の活躍によって多言語対応能力が高まり、訪日外国人へのサービスの向上にも繋がります。外国人労働者は、海外市場への進出やマーケティングでも即戦力となり得るでしょう。
さらに、日本人従業員にとっても、外国人労働者との日常的な交流を通じて異文化コミュニケーション能力や語学力が向上することが期待できます。外国人労働者を受け入れることはグローバル人材の育成にも繋がり、組織全体の国際感覚が磨かれていくでしょう。
教育・サポート体制の重要性
外国人労働者を受け入れる際には、教育・サポート体制を整備し、定着率向上や早期戦力化に繋げることが重要です。ここでは、教育拠点や研修体制、生活・言語支援、教育・サポート体制によって企業側に生まれるメリットについて解説します。
教育拠点・研修体制の有無
外国人労働者を受け入れる際には、研修体制をしっかりと整備することが重要です。外国人労働者の教育拠点には、一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)や一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)などの実践的な日本語教育や就労支援を行う組織や、ハローワークの役割を果たす外国人雇用サービスセンター、技能実習生向けの地方の教育訓練施設、政府の支援機関である外国人技能実習機構などがあります。
上記のような教育拠点では、日本語研修や文化研修、専門スキル習得、就職支援、生活定着サポートなど、多様なニーズに対応した取り組みを行っています。
ほかにも、大手企業や特定技能人材の受け入れ企業では、社内に日本語教育やOJT専用の訓練設備を整えるケースもあり、教育拠点として活用することが可能です。また、地方などでも場所を問わず学習ができるよう、eラーニングやオンライン教育、動画教材やスマホ学習の導入も推進されています。
生活・言語支援の内容
外国人労働者の生活支援は、外国人在留支援センターや地方自治体の窓口に相談したり、生活ガイドブックなどを多言語で提供する外国人生活支援ポータルサイトを参考にしたりするとよいでしょう。外国人労働者が安心して生活できるように、企業は支援計画の作成や多言語での情報提供、日本人との交流機会の創出などを実施することが大切です。
また、採用後に外国人労働者の日本語のスキルが上達するか、コミュニケーションが適切にとれるようになるかどうかは、企業の日本語教育に左右される部分が大きいです。外国人労働者に対する日本語教育には、主に「受け入れ企業が実施する研修に参加する」「入社前・入社後に日本語学校に通う」「ボランティアの日本語教室に通う」などの方法が考えられます。
具体的には、日本語ならではの発音や、日本での生活に必要なフレーズ、ビジネス用語、日本文化を背景とした返答方法などを学ぶのが一般的です。
企業側に生まれるメリット
外国人労働者への教育・サポート体制を充実させることは、外国人労働者本人の安心に繋がるだけでなく、企業にとっても業務効率化や生産性向上などのメリットに繋がります。また、適切な教育やサポートによって外国人労働者の定着率を高められれば、新たな採用や新人教育にかかるコストと手間を大幅に削減することが可能です。
さらに、多様性を重視する姿勢は企業イメージを高め、国内外問わず優秀な人材を引きつける魅力となります。企業ブランドや競争力の向上も期待でき、企業全体としても成長していくことが可能でしょう。
技能実習から育成就労へ
外国人労働者の在留資格のうち「技能実習制度」に関する課題と、2027年4月から開始される育成就労制度の概要をわかりやすく解説します。
技能実習制度の課題
技能実習制度とは、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転することによって、その地域等の経済発展を担う人材育成に寄与することを目的とした制度です。1993年に創設された後、2017年11月には「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、現在の技能実習制度となっています。
技能実習には1号から3号まであり、1年目は技能実習1号として講習や実習で学び、2〜3年目は技能実習2号として実習を行い、4〜5年目は技能実習3号としてさらに実習を行います。ただし、1号から2号、2号から3号へ進むためには、試験に合格しなければなりません。また、技能実習3号の実習開始前または開始後1年以内に、1ヵ月以上の一時帰国も必要です。
技能実習制度は日本の人手不足を解消するためのものではなく、あくまでも開発途上国等の人材育成をすることが主な目的です。しかし、実際には国内の労働力とされている現実があり、本来の目的と実態が乖離していることが問題となっています。
また、技能実習生の立場の弱さが問題となっているケースもあります。受け入れ企業や監理団体による技能実習生の人権を侵害する行為や、立場の弱さが原因とみられる技能実習生の失踪など、さまざまなトラブルが発生している点も大きな問題です。
育成就労制度でどう変わるか
育成就労制度とは、技能実習制度に代わり、日本の人手不足を解消するために外国人労働者の育成や人材確保を目的として創設された制度です。育成就労制度を利用する際の在留資格は、「育成就労」といいます。
技能実習制度は、発展途上国の人材育成による国際貢献が主な目的であったのに対し、育成就労制度は、日本の発展のための人材育成と人材確保を目的としている点が大きな違いです。具体的には、外国人材を3年間の育成期間で特定技能1号の水準に育成することが目標で、特定技能制度と連続性をもたせる形で設計されているのが育成就労制度の特徴です。
これまでの技能実習制度の問題点をもとに、育成就労制度は人材確保と人材育成を目的とするなど、実態に即した制度となるように見直しがされています。さらにキャリアパスを明確化し、外国人材に日本が選ばれるように技能・知識を段階的に向上させられるような制度となるように制度設計されています。
育成就労制度は、2024年に基本方針・主務省令等の作成が行われ、分野別運用方針の作成や事前申請期間を経て、2027年より施行開始となる予定です。
まとめ
外国人労働者の受け入れは、日本における深刻な人手不足問題の解消はもちろん、多様な視点・創造性の導入や国際化の推進など、企業の成長にとっても重要な役割を担います。ただし、外国人労働者を適切に活用するためには、労働環境や待遇、賃金、業務内容、労働時間などについて、入管法や労働基準法などの法令を正しく理解して遵守することが必須です。
また、外国人労働者が日本で安心して働くためには、就労関係のサポートだけでなく、生活面でのサポートも重要です。慣れない環境での労働や生活はストレスや孤立感を感じやすいため、相談しやすい環境整備や文化・生活面での配慮、社内体制の強化などが求められます。必要に応じて外部機関との連携も行いながら、外国人労働者のサポート体制を整えていきましょう。
2027年より施行開始となる育成就労制度についても制度の目的や内容を正しく理解し、外国人労働者の在留資格に応じて適切な雇用ができるようにしておきましょう。
株式会社ONODERA USER RUNは、日本語・特定技能の専門教育から人材紹介、就業後の生活や資格取得に向けた学習支援までをワンストップで行い、安定して長く働ける人財をご紹介しております。
自社無償教育拠点である「OUR BLOOMING ACADEMY」で教育した海外人材の紹介や、初めての受入れでも安心な登録支援サービス、外国人の定着に向けた生活支援サービスなど、充実したサポート体制を整えております。人手不足や外国人の受け入れなどについてお困りごとがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説
- ARCHIVE
-
-
- 2026年
-
- 2020年
-