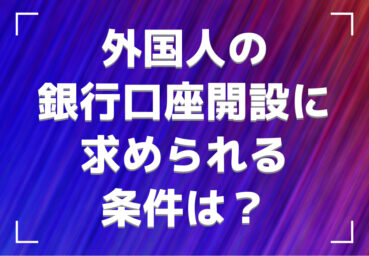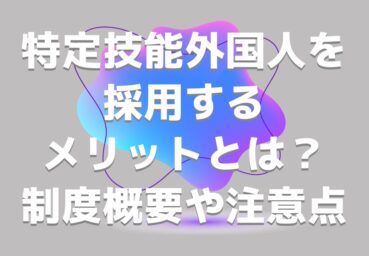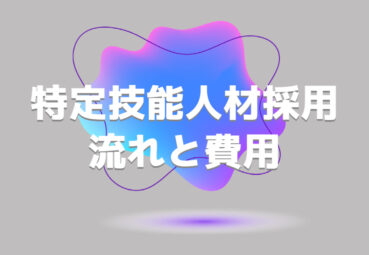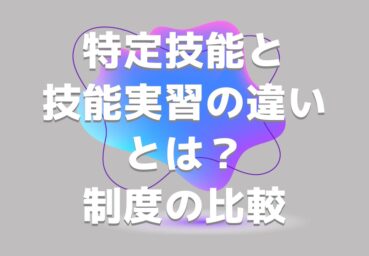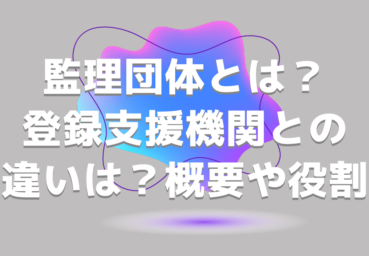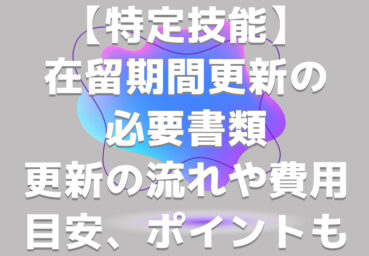特定技能関連

特定技能や技能実習制度を活用し、ウズベキスタン人を採用している企業は増えつつあります。なかには、ウズベキスタン人を採用するにあたって、理解を深めたいと考える採用担当者の方もいるでしょう。
この記事では、ウズベキスタンという国の概要に加え、ウズベキスタン人の特徴や採用するメリットを解説します。併せて採用時の流れやポイントについても解説しますので、ぜひ特定技能で採用する際の参考にしてください。
目次
ウズベキスタンとはどのような国?

まずは、ウズベキスタンという国の概要や特徴を見ていきましょう。以下は、ウズベキスタンに関する基本情報です。
|
面積 |
44万8,969平方キロメートル |
|
人口 |
3,570万人 |
|
首都 |
タシケント |
|
言語 |
ウズベク語(国家語)、ほかロシア語 |
|
宗教 |
イスラム教スンニ派が主 |
|
主要産業 |
綿繊維産業、食品加工、機械製作、ほか金や石油、天然ガスなど |
|
日本との関係 |
良好に進展。人的交流も活発。 |
ウズベキスタン共和国は、中央アジアに位置する内陸国です。教育に関しては、初等教育~中等教育までが無償で提供されており、識字率はほぼ100%と高い水準です。
2019年12月には、ウズベキスタン共和国と日本との間で特定技能制度に関する協力覚書の署名・交換が行われています。その後、特定技能人材の送り出し・受け入れが開始され、2020年6月末時点で3人のウズベキスタン人が受け入れられました。
出典:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数の公表(令和4年以前)
日本におけるウズベキスタン人の在留状況
出入国在留管理庁の調査によると、2024年12月時点での在留ウズベキスタン人の人数は7,621人です。在留資格別では「留学」が最も多く3,047人、次いで「家族滞在」が1,332人です。さらに、技術者や会社員として企業で働く「技術・人文知識・国際業務」での在留者が1,238人と続きます。
「特定技能」の在留資格を持つウズベキスタン人は72人となっており、上記と比べれば少ない状況です。
また、過去のデータと比較すると、ウズベキスタン人の在留数は増加傾向にあります。以下は、2021~2024年分のウズベキスタン人における在留状況の推移です。
|
2021年 |
3,781人 |
|
2022年 |
5,970人 |
|
2023年 |
7,086人 |
|
2024年 |
7,621人 |
出典:出入国在留管理庁|【在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】
ウズベキスタン人の特徴や国民性
続いて、ウズベキスタン人の特徴や国民性について解説します。
親しみやすい性格の人が多い
ウズベキスタン人は親日感情が高く、初対面でも積極的に笑顔や挨拶を交わして関係を築くことが多い傾向にあります。ウズベキスタンには人とのコミュニケーションを重視する文化があるため、チームや共同での作業でも円滑にかかわれる人材が多いといえるでしょう。
日本での受入れ企業からは、親しみやすさから早期に職場に溶け込める人材が多いという声も少なくありません。
温厚で優しい性格の人が多い
ウズベキスタン人は温厚で礼儀正しく穏やかな人柄の人が多いのが特徴で、日本の職場文化にも適応しやすいとされています。表面的な衝突が少なく協調性を重んじるため、職場での人間関係構築がスムーズに進む傾向にあります。
また、上下関係を重視し指示を守る姿勢が見られるウズベキスタン人も少なくないことから、信頼できる人材として職場で受け入れられやすいでしょう。
勤勉で安定志向の働き方を好む人が多い
ウズベキスタン人は家族や親族への責任感が強く、「家族のために働く」という意識を持つ人も多いのが特徴です。
また、努力を重要視し、指示を正確に実行しようという姿勢を持つ傾向にあります。そのため、真面目で職場に長期定着しやすく、雇用環境への対応力・定着力の高さがあることも特徴です。
ただし、時間に対する認識や使い方が日本とは異なるため、なかには時間についてルーズと受け取られるような行動を取る人もいるでしょう。その反面、時間を含めきちんと説明すれば日本のルールに合わせられる柔軟さも持っています。
イスラム教を基盤とした生活文化がある
ウズベキスタン人の9割近くはスンニ派イスラム教徒であり、社会や生活習慣において宗教の価値観が大きく影響しています。なお、ほかの宗教はシーア派イスラム教、ロシア正教、ユダヤ教、仏教、キリスト教などです。
戒律はあまり厳しくなく、例えば「豚肉食」がタブー視されることは少ない傾向にあります。そのほか、飲酒や女性の自由な服装も許されています。
ただし、なかには食事に気を使ったり礼拝をしたり、ラマダン(断食)などを行う人もいるため、その場合は人材に合わせた環境の整備が求められることもあるでしょう。
また、ウズベキスタン人は伝統行事や家族との関係を重視する傾向にあることから、日本で就労する場合、家族と離れることへの配慮やサポートが必要になるケースがあります。
複数の言語を使うことが多い
ウズベキスタンでは、ウズベク語に加えてロシア語も広く使われており、日常的に2~3言語を駆使するバイリンガルやマルチリンガルな人も少なくありません。
近年では英語教育にも力を入れているなど、日本語を含めた複数言語を学ぶ柔軟性が文化的に根付いています。また、ウズベク語は文法構造が日本語と似ていることから、日本語の習得が比較的スムーズという特徴もあります。
特定技能でウズベキスタン人を採用するメリット

ウズベキスタン人材の受け入れには、以下のようなメリットが期待できます。
- ・若くて意欲的な労働力を確保しやすい
- ・学習意欲が高く多言語の環境に適応しやすい
- ・技術職分野における適性と定着率の高さがある など
若いウズベキスタン人材は海外での就労に意欲的かつ、現地で日本語や専門的な技能を学んでいる場合が多いため、即戦力としての活躍が期待できます。また、日本語はもちろん英語を使いこなせるウズベキスタン人も少なくないことから、多言語の環境に適応できる人材の確保が期待できます。
加えて、ウズベキスタン人材には手先が器用かつ細かい作業でも丁寧にこなせる人が多く見られることから、製造業や建設などの分野の適性が高い点も強みです。さらに、「家族のために働く」という価値観と真面目さから定着率が高く、長く働き続けてくれる傾向にもあります。
-
ウズベキスタン人材をはじめとした外国人を雇用するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
-
ウズベキスタン人材を採用できる特定技能分野

-
現在ウズベキスタン国内において特定技能の試験を受験できるのは「介護」「農業」「建設」の3分野です。ただし、今後ほかの分野でも試験を受験し採用できるようになる可能性があります。
ここでは、上記3つの特定技能分野について詳しく解説します。
-
介護
-
介護分野では、入浴や食事、排泄などの身体介護に加え、レクリエーションや機能訓練の補助などに従事します。特定技能「介護」を取得するには、日本語能力試験(N4以上)と介護技能評価試験、介護日本語評価試験の合格が必要です。
ウズベキスタン人材は礼儀正しい国民性と手先の器用さが評価されており、介護をはじめとした丁寧な対応が求められる職種においても順応性が高いとされています。
-
農業
-
農業分野では、畑作、施設園芸、畜産などの業務が対象で、季節や地域によって業務内容は多岐にわたります。
ウズベキスタンは農業国であり、農作業に慣れている人材が多く日本の農業にも適応しやすいという背景から即戦力としての活躍が期待できるでしょう。特定技能の試験では農業知識と一定レベルの日本語能力が求められ、ウズベキスタン国内でも対策講座が広がっています。 -
建設
-
建設分野では、型枠施工や土工などの土木区分、鉄筋施工、とび、建築大工などの建築区分、電気通信、配管などのライフライン・設備区分に該当する業務に従事できます。建設の特定技能で業務に従事するには、技能評価試験(または技能検定)と日本語試験の合格が必須です。
ウズベキスタン国内では、日本語教育や建築技術の訓練機関も増えつつあり、建築分野において一定の技能を持つ候補者が多い傾向にあります。
-
ウズベキスタン人材を特定技能で採用する流れ
-
ウズベキスタン人材を特定技能で採用する際は、「人材をウズベキスタンから受け入れる場合」と「日本に在留しているウズベキスタン人材を受け入れる場合」で異なります。以下は、それぞれのケース別の流れです。
【人材をウズベキスタンから受け入れる場合】
1.雇用契約を締結する
2.在留資格認定証明書の交付申請
3.契約の相手方へ在留資格認定証明書を送付し、相手方が在ウズベキスタン日本国大使館に特定技能の査証発給申請を行う
4.相手方は上陸審査を経て、特定技能の在留資格が付与され、入国および在留を開始
【日本に在留しているウズベキスタン人材を受け入れる場合】
1.雇用契約を締結する
2.在留資格変更許可申請
なお、ウズベキスタン人材を特定技能外国人として受け入れる場合、ウズベキスタン政府の承認や許可を受ける必要はありません。
-
ウズベキスタン人材を特定技能で採用する際の5つのポイント

- 続いて、ウズベキスタン人材を特定技能で採用する際に心がけるべきポイントについて解説します。
-
特定技能制度に沿った手続きを行う
-
特定技能外国人を受け入れるには、受入れ企業が所定の条件を満たしているとともに、労働基準法や最低賃金法の順守が必須です。これには、就業条件を明確に記載した雇用契約書の作成なども含みます。
また、受け入れ計画書や雇用状況報告などの各種届出を期限内に提出する義務もあります。虚偽申請や不正な受け入れは、制度利用停止のリスクがあるため注意が必要です。
したがって、ウズベキスタン人材を特定技能で受け入れる際は、制度に沿った手続きを漏れなく行うように心がけましょう。
-
在留資格に合った業務内容に従事させる
-
ウズベキスタン人材がおもに取得する「特定技能1号」は、定められた16分野の業務のみ従事可能です。前述のとおり、ウズベキスタン国内で試験を受けられるのは16分野のうち「介護」「農業」「建設」の3分野となるため、受け入れ先もこれらの分野が中心となるでしょう。
ウズベキスタン人材の受け入れに限らず、特定技能では分野外の業務や雑務を兼任させることは制度違反となるため注意が必要です。場合によっては、ウズベキスタン人材も在留資格の取り消し、出国命令などの罰則を受ける恐れがあります。 -
文化・生活習慣・価値観に配慮したサポートを実施する
-
ウズベキスタンはイスラム教圏であり、比較的柔軟ではあるものの、なかには受け入れにあたって食事や宗教行事への配慮が必要となる場合があるでしょう。人材それぞれの文化や価値観にあったサポートを適切に実施することが重要です。
併せて、暮らしの違いによるストレスを軽減するため、ゴミ出しや交通ルール、公共マナー、地域生活など日本の生活様式の説明を行うことも大切です。これらの支援については、以下の記事でも詳しく解説しています。
-
日本語学習のフォローを行う
-
特定技能の取得には日本語試験の合格が必須となるため、ウズベキスタン人材はある程度の日本語能力を有した状態での採用が可能です。とはいえ、採用後も日本語能力向上をサポートすることで、業務効率や職場定着率の向上が期待できるため、継続して日本語学習のフォローを行うのがおすすめです。
例えば、通訳サポートや日本語教室の紹介などが効果的です。日本語学習をサポートし日本語能力をより高めることで、業務面やコミュニケーション面での不安解消に繋がります。
-
登録支援機関を活用する
-
企業単独でのウズベキスタン人材の受け入れや支援が難しい場合は、登録支援機関を活用するのもポイントです。登録支援機関には、支援計画の作成サポートや履行、生活支援、行政手続きなどを委託できます。
コミュニケーションの課題やトラブルにも対応できるため、これらに不安がある企業にとって、登録支援機関の活用は人材をスムーズに受け入れるうえで効果的といえるでしょう。
登録支援機関について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
-
ウズベキスタン人材の受け入れサポートはオノデラユーザーランへご相談を
-
ウズベキスタン人材の受け入れをはじめ、特定技能で外国人材の採用を検討したいと考えている採用担当者の方は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)へご相談ください。
オノデラユーザーランは、アジア各地に展開する自社の教育拠点にて特定技能と日本語の無償教育を実施しています。外国人材の紹介では、企業様のニーズをしっかりとヒアリングしたうえで最適な人材を紹介可能です。
また、オノデラユーザーランは登録支援機関としてさまざまな支援サービスを提供しているのも特徴です。特定技能人材の入国、入国後の日本語学習機会の提供や相談・苦情への対応、定期的な面談など一括でサポートいたします。外国人材の受け入れを初めて行う場合も、安心してお任せください。
-
まとめ
-
ウズベキスタン人は、親しみやすい性格かつ勤勉、安定志向の働き方を好む人が多く、上下関係や協調性を重視するといった特徴があり、日本の労働環境にも馴染みやすいといえます。特定技能で受け入れることで、若く意欲的な人材を即戦力として確保できるほか、長く職場に定着してくれるメリットも期待できるでしょう。
ウズベキスタン人材を特定技能で受け入れる際は、特定技能制度を順守して手続きや労働環境、労働条件の整備を行うことが重要です。併せて、文化や生活習慣、価値観に配慮して業務や日々の生活をサポートするように心がけましょう。
ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)は、特定技能外国人の教育や紹介、定着まで一括でサポートしています。今年、11月にはウズベキスタンにて自社無償教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMYウズベキスタン」を開校し、教育を開始する予定です。
-
ウズベキスタン人材の雇用を検討している採用担当者の方は、ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください。
お問い合わせはこちら
2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説
- ARCHIVE
-
-
- 2026年
-
- 2020年
-