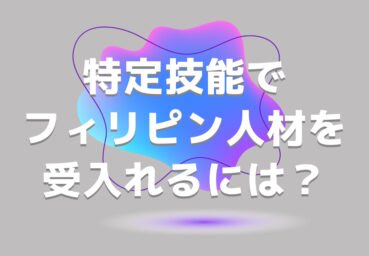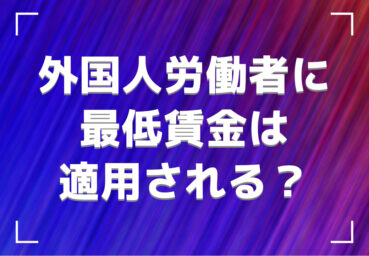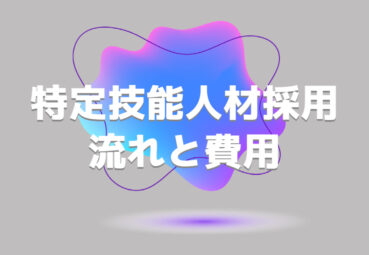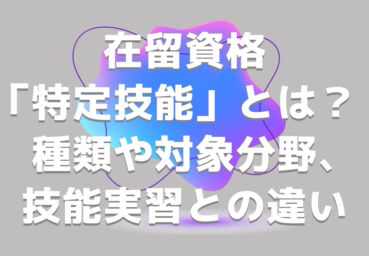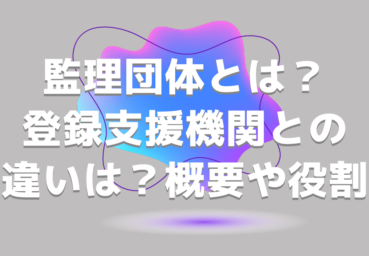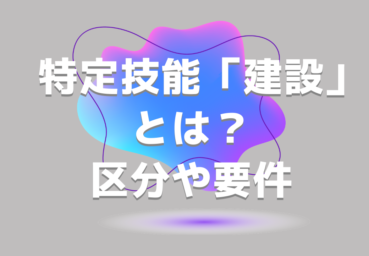特定技能関連

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、日本政府は特定技能制度を創設し、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを推進しています。アジア圏を中心に多くの労働者が日本で働いており、そのなかには真面目で親日的なミャンマーからの人材も多くいます。
今回はミャンマー人の在留状況や国民性を紹介し、特定技能でミャンマー人を採用するメリットや一緒に働く際の注意点、採用の流れについて解説します。外国人労働者の雇用を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
【基礎知識】ミャンマー人の在留状況
出入国在留管理庁の「令和5年末現在における在留外国人数について」によると、日本に在留しているミャンマー人の数は2023年12月末時点で86,546人です。2022年12月末時点の在留ミャンマー人は56,239人だったため、1年間で3万人以上増加したことになります。
参考:出入国在留管理庁|令和5年末現在における在留外国人数について
ミャンマー人の在留者数が急増している背景には、2021年2月にミャンマー国内で発生した軍事クーデターによる武力衝突や経済的混乱があります。クーデターにともない多くのミャンマー人が避難生活を強いられており、このような状況を脱するため日本で働こうと考えた人が増えているのです。
特定技能のミャンマー人の在留者数
出入国在留管理庁の「特定技能制度運用状況」によると、特定技能のミャンマー人の在留者数は2024年6月末時点で19,059人です。2023年6月末時点の特定技能人材の在留者数は8,016人であるため、この1年間で1万人以上も増加していることがわかります。
〈国籍・地域別特定技能在留外国人数(2024年6月末時点)〉
|
国籍・地域 |
人数 |
割合 |
|
ベトナム |
126,832人 |
50.4% |
|
インドネシア |
44,305人 |
17.6% |
|
フィリピン |
25,311人 |
10.1% |
|
ミャンマー |
19,059人 |
7.6% |
|
中国 |
15,696人 |
6.2% |
|
カンボジア |
5,461人 |
2.2% |
|
ネパール |
5,386人 |
2.1% |
|
タイ |
5,178人 |
2.1% |
|
その他 |
4,519人 |
1.8% |
|
計 |
251,747人 |
100% |
参考:出入国在留管理庁|特定技能制度運用状況(令和6年6月末)
2019年4月に特定技能制度が創設されて以降、特定技能外国人として働くミャンマー人は急増しています。ミャンマー国内の政治・経済状況もあり、今後も労働者として来日するミャンマー人は増えていくでしょう。
【基礎知識】ミャンマー人の国民性

特定技能の人材としてミャンマー人を受け入れるにあたって知っておきたいのが、ミャンマー人の国民性です。ここで紹介する特徴がすべてのミャンマー人に当てはまるわけではありませんが、全体的な特徴として知っておくとよいでしょう。
仏教徒が多い
ミャンマー人の90%は仏教を信仰しており、生活のあらゆる面で仏教精神が根付いています。寺院や僧侶に対する信仰心も強く、宗教行事にも積極的に参加する傾向があり、それを通じてコミュニティの結束を高めているといわれています。
ミャンマー人が信仰する仏教は「上座部仏教」であり、日本人が信仰する「大乗仏教」とは異なる点が多くあります。上座部仏教は瞑想や参拝を日常的に行うことが多く、仏教が生活の一部になっているといえるでしょう。
|
上座部仏教 |
大乗仏教 |
|
|
別名 |
小乗仏教 テーラワーダ仏教 南伝仏教 |
北伝仏教 |
|
目指す方向 |
個人の悟りを追求 |
すべての存在の救済を目指す |
|
救われる対象 |
修業した僧侶 |
すべての人 |
|
信仰の対象 |
お釈迦様のみ |
お釈迦様をはじめとし、如来、菩薩など |
|
戒律 |
お釈迦さまが説かれた原始的な教義を保持 |
宗派ごとに異なる |
ミャンマー人の性格や価値観にも、仏教の教えが強く反映されています。仏教への理解があるとミャンマー人への理解も深まるかもしれません。
温厚で自己主張が少ない
ミャンマー人は温厚で優しい性格の方が多く、人前で怒ることはほとんどないといわれています。これは「徳を積むことが幸福に繋がる」という仏教の教えを尊重しているためであり、ミャンマーでは徳を重視することで人に対して優しく接する文化が根付いるようです。
また、ミャンマー人は素直・真面目で自己主張も少ない傾向にあるため、同じく真面目で控えめな傾向にある日本人との相性が良いのも特徴です。
親日的である
ミャンマーは東南アジア諸国において特に親日的な国として知られています。ミャンマーの独立に日本が貢献したことや、日本が多額のODA(政府開発援助)を行っていることなどが要因と考えられます。
日本人に対して偏見や嫌悪感を持っているミャンマー人は少ないため、良好な関係を築きやすいでしょう。また、日本の漫画やアニメが好きな方も多いので、親しみを持ちやすいのも特徴です。
家族を重んじる
ミャンマー人は家族をとても大切にする傾向があります。特に親を敬う気持ちが強く、就職や結婚といったライフイベントで家族の意見が尊重されやすくなります。家族で集まる機会も多く、人との繋がりを重視することが多いようです。
また、親だけではなく、目上の人や年長者に対する敬意も強いため、年長者を相手にする職場でも丁寧に対応できる可能性が高いでしょう。
挨拶をする習慣がない
ミャンマー語には「おはようございます」「お疲れ様です」といった決まった挨拶の言葉がありません。ミャンマー人は挨拶をする習慣自体がなく、不慣れなうちは挨拶に躊躇することもあるかもしれません。
特定技能でミャンマー人を採用するメリットは?

特定技能の人材としてミャンマー人を採用するメリットを5つ紹介します。
真面目で勤労意欲が高い
一般的にミャンマー人は真面目で勤勉であり、なおかつ勤労意欲が高い傾向にあります。その要因の一つとされるのが高校卒業の際に受ける「統一試験」です。統一試験の結果がその後の生活にも影響をおよぼすこともあることから、その勉強によって努力を惜しまない習慣を得る方が多く、仕事に真摯に向き合ってくれるでしょう。
納期や品質に対する意識も高いため、期日を重視する日本の労働環境に適応している方が多いといえます。加えて、日本はミャンマーに比べて平均賃金が高いこともミャンマー人のモチベーション向上に繋がるでしょう。
また、ミャンマー人の勤勉さは日本人労働者にも良い影響を与える可能性があります。ミャンマー人の採用や勤務態度が刺激となり、より意欲的に仕事に取り組むようになるかもしれません。
日本語の習得スピードが早い
ミャンマー人の公用語であるミャンマー語(ビルマ語)は、日本語と文法や発音が似ています。そのため、ミャンマー人は勤勉さも相まって日本語の習得スピードが早い傾向です。
外国人労働者の採用にあたって課題の一つのなるのが言語です。他の外国人より日本語へのハードルが低い傾向にあるミャンマー人なら、安心して採用しやすいでしょう。
若い人材を確保しやすい
日本貿易振興機構の「【ミャンマー】国勢調査に見る市場像」によると、2014年のミャンマー人の平均年齢は27.1歳です。一方、総務省統計局の「令和2年国勢調査」によると、2020年時点での日本人の平均年齢は47.6歳となっており、ミャンマーと日本では平均年齢に大きな差があることがわかります。
参考:日本貿易振興機構|【ミャンマー】国勢調査に見る市場像(2015年9月)
日本では少子高齢化により若い人材の獲得競争が激化していますが、日本より平均年齢がとても低いミャンマーなら、若い人材を確保しやすいでしょう。
また、ミャンマー人のなかには家族を呼んで日本に永住できるよう、家族の帯同が認められる特定技能2号への移行を検討している方も少なくありません。特定技能2号になれば更新し続けることで、在留期間の制限がなくなるため、雇用する側も長期的な視点で採用できるようになります。
特定技能1号・2号の違いは?それぞれの取得方法もわかりやすく解説
介護職の希望者が多い
ミャンマー人は仏教の教えで徳を積むこと、年長者を敬うことを重要視しているため、特定技能における介護分野への参入を希望する方も多くいます。
日本は高齢化が進んでおり、介護職のニーズがますます高まっているため、介護分野を志望するミャンマー人の存在は貴重です。
特定技能「介護」とは?対応できる業務や取得方法、受け入れ側の注意点を解説
日本に馴染みやすい
ミャンマー人は親日的であり、性格も日本人と似ている場合が多く、日本での暮らしに馴染みやすいでしょう。仕事でもプライベートでも区別なく友好を深める傾向があるので、一緒に働きやすい人柄の人が多いといえます。
特定技能のミャンマー人と一緒に働く際の注意点

働き手として魅力の多いミャンマー人ですが、一緒に働く際には注意すべきこともあります。特定技能のミャンマー人と一緒に働く際の注意点を3つ解説します。
人前で叱責しない
一般的にミャンマー人は温厚なので、他人から叱られた経験が少ない傾向にあります。人前で叱られることにも慣れていないため、職場で叱責してしまうと、想像以上にショックを与えてしまうかもしれません。
人前でミスを指摘するのは避けるとともに、ミスをした場合でも優しく指摘し、フォローを忘れないようにしましょう。
積極的に声をかける
ミャンマー人は自己主張が少ない傾向のため、自分から悩みや不安を言い出せない方もいます。また、寂しがり屋の方が多いので、こちらから積極的に声をかけてあげることが大切です。
ミャンマー人の同期や同僚、先輩がいると安心感が増すため、ミャンマー人を雇用する際は複数人雇用も検討してみましょう。
価値観や文化を尊重する
ミャンマー人と日本人は信仰する宗教や育った環境が異なるため、考え方や行動にも違いがあります。良好な関係を築くためには、ミャンマー人の価値観や文化を尊重することが大切です。
また、先述のとおりミャンマー人は挨拶の習慣がないので、必要に応じて挨拶のマナーやタイミングを教える必要があります。互いの文化や習慣を尊重しながら、気持ち良く働ける職場づくりを目指しましょう。
特定技能でミャンマー人を採用する際の流れ

特定技能の人材であるミャンマー人の採用方法は、海外現地在住者と日本在住者で異なります。それぞれ、採用の流れを見ていきましょう。
参考:法務省|~特定技能外国人の受入機関の方々へ~ ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
海外現地在住者を採用する場合
海外に在住するミャンマーの特定技能人材を受け入れるためには、ミャンマー国内の認定送出機関を通じて手続きする必要があります。海外現地在住者を採用する流れは以下のとおりです。
- 1.求人票の提出
ミャンマー政府認定の送出機関を通じて、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に求人票を提出します。
- 2.求人票の許可・承認
MOLIPの承認と許可を受け、認定送出機関が求人票をもとに人材を募集し、受入れ企業側は送出機関からの人材紹介を受けます。
- 3.雇用契約の締結
最適な人材が見つかったら、雇用契約を締結します。
- 4.在留資格認定証明書の交付申請
受入れ企業が地方出入国在留管理官署に対して、特定技能にかかる在留資格認定証明書の交付申請を行います。
- 5.海外労働身分証明カード(OWIC)と査証の発行申請
特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方が、MOLIPに海外労働身分証明カード(OWIC)の申請を行います。また、手順4で交付された在留資格認定証明書を在ミャンマーの日本大使館に提示し、特定技能にかかる査証発給申請を行います。
- 6.特定技能外国人として入国・在留
上記手続きが終了後、日本での上陸審査を行い、上陸に問題がなければ上陸が許可されます。それによって特定技能の在留資格が付与され、受入れ企業で働けるようになります。
日本在住者を採用する場合
日本在住者を採用する場合は、海外在住者を採用するのに比べて手続きがそれほど多くありません。日本在住者を採用する際の流れは以下のとおりです。
- 1.雇用契約の締結
受入れ企業が特定技能にかかる雇用契約を締結。海外在住者の採用と異なり、日本の受入れ企業がミャンマー国籍の方に対して直接採用活動を行います。
- 2.パスポートの更新申請
雇用契約を締結したミャンマー国籍の方が、在日本ミャンマー大使館でパスポートの更新(申請)を行います。
- 3.在留資格変更許可申請
雇用契約を結んだミャンマー国籍の方が地方出入国在留管理官署に対し、特定技能への在留資格変更許可申請を行います。申請が受理され、在留資格の変更が許可されれば、特定技能外国人として働けるようになります。
特定技能でミャンマー人を採用するなら「オノデラユーザーラン」へ
特定技能でミャンマー人の採用をお考えなら、外国人材紹介会社ONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談ください。
オノデラユーザーランでは、人材募集から教育、紹介、入社準備、入社後の定着支援まで自社で行っています。外国人材と受入れ企業の双方がより良い関係を築けるよう一気通貫でサポートしているため、安心して外国人材との雇用契約を締結できるでしょう。
自社アカデミーで特定技能外国人の教育も行っており、2024年10月末時点で、特定技能試験合格者数は5,300名を超えています。ミャンマー人の紹介実績も多数あるため、ミャンマー人の雇用に興味がある方はぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
まとめ
温厚で真面目なミャンマー人は日本人との相性が良く、働き手としても優秀です。ミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる際は、ミャンマー人の特性をよく知り、気持ち良く働ける環境づくりを心がけましょう。
ミャンマー人の特定技能人材を受け入れたいとお考えの方は、ぜひONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)にご相談ください。優秀なアジアの人材が働けるよう採用後のサポートもあるため安心して外国人材を受け入れられるでしょう。
お問い合わせはこちら
2019年4月に創設された、人材の確保が困難な16の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる在留資格のこと。
在留資格「特定技能」とは?種類や対象分野、技能実習との違いなどをわかりやすく解説
外国人労働者受け入れのメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
外国人労働者受け入れの現状は?雇用のメリット・デメリットや問題点、流れなどを徹底解説
- ARCHIVE
-
-
- 2026年
-
- 2020年
-